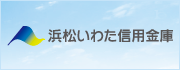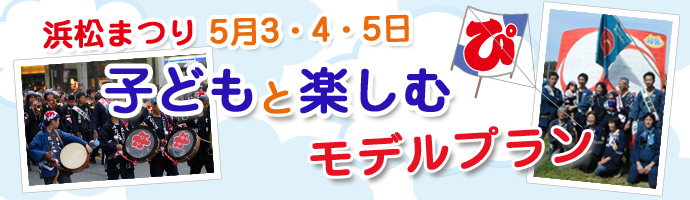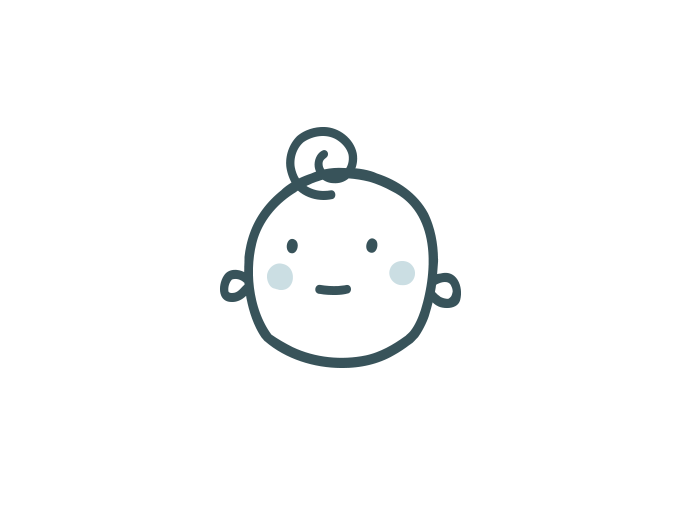子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
特集記事を検索
見るより参加がだんぜん楽しい!親子で浜松まつりデビュー
写真提供:浜松・浜名湖ツーリズムビューロー
4月になると聞こえてくる「浜松まつり」のラッパやお囃子の音。周囲の友達から聞いて「浜松まつりに出てみたい」と言う子どももいるかもしれません。ぴっぴの特集記事では、過去に初子祝いの様子や、子どもラッパ隊・お囃子に参加する子どもたちの様子を取材しました。
今回は一般参加として単純にまつりに出たい・楽しみたいというファミリーに向け、浜松まつりの参加方法や、実際に参加した親子の体験談などを紹介します。
「浜松まつり」ってどんなおまつり?
子どもの誕生を祝うために毎年5月3日~5日に開催される市民のまつり・浜松まつり。戦国時代に引間城主の長男の誕生を祝って凧を揚げたことがはじまりの一つと言われています。市内から170以上の町が参加し、昼は凧揚げ合戦、夜は御殿屋台引き回しを3日間にわたって行います。
どんなことをするの?
実際には何をするのでしょうか。浜松まつり会館館長・中村敏幸さんにお話を伺いました。

【昼】凧揚げ合戦
中田島会場で行われる凧揚げ合戦には、初子(はつご)の誕生を祝う「初凧」、大凧の凧糸を絡ませ切りあい各町が競う「糸切り合戦」があり、「子どもラッパ隊」の子どもたちがラッパを吹いて場を盛り上げます。また5日のこどもの日の午前中には「子ども凧揚げ」があり、各町の凧を子どもたちの手で揚げることができます。

【夕方】子ども練り
「練り」とは、町の人が列をなしラッパや太鼓のリズムに合わせて「オイショ」、または「ヤイショ」のかけ声をかけながら練り歩くことで、子どもだけで町内や初子のお宅をまわる「子ども練り」を行う町もあります。練りの後にはお祝いのお礼としてお菓子やジュースがふるまわれることが多いです。
【夜】御殿屋台引き回し・練り
豪華絢爛な御殿屋台を引いて夜の町内や街中を練り歩く御殿屋台引き回し。それを彩るのが、子どもたちが屋台の上で鐘や太鼓などを奏でる「お囃子」です。お囃子以外の子どもは、大人と一緒に屋台を引きます。
夜には初子のお宅で町の代表がお祝いの言葉を述べた後、子どもの成長を願うための「初練り」が盛大に行われます。
どうすれば参加できるの?
浜松まつりは町単位で参加します。
1.法被とワッペンを手に入れる

必須なのが、参加する町の法被とワッペンです。法被は事前に注文して購入します。ワッペンは浜松まつりの正式な参加証のようなもので、町名と年度、番号が書かれており、毎年色が異なります。参加する家族の人数分を購入し、法被の袖に縫い付けます。申込方法や費用は、3月頃から町内の回覧板で案内されることが多いです。
2.集合時間や場所を確認する
ワッペンを購入する際や回覧板で、当日の集合時間や場所などのスケジュールが知らされます。凧揚げ会場には毎朝各町から貸切バスやタクシーなどが出ます。町の人と一緒に凧揚げ会場に行きたい場合はバスの集合時間や場所を確認しておきましょう。また、夜の御殿屋台引き回しや練りは、街中に出る日もあれば町内をまわる日もあり、時間や場所が日によって異なります。集合場所や時間も変わるため、事前の確認が必要です。
気になる服装 法被の中には何を着ればいい?
法被とワッペンがあれば参加はできますが、町によっては「正装」が必要なところも。浜松まつりの正装には何を着ればいいか、市内でまつり用品を製造・販売している株式会社山崎の折尾剛実さんにくわしく教えてもらいました。
基本アイテム:腹掛け、鯉口シャツ、股引、地下足袋

- 腹掛け
腹の部分に大きなポケットが付いていて「どんぶり」とも呼ばれます。エプロンのようにひもを腰のあたりでしばって身に着けます。 - 鯉口シャツ
腹掛けの中に着るシャツ。さまざまな柄のものがあります。 - 股引(ももひき、またびき)
ズボンのようなもので、昔ながらの紐タイプや、脱ぎ履きしやすいウエストがゴムのタイプがあります。 - 地下足袋
足首の部分をこはぜ(金具)やマジックテープ、ファスナーなどで留めます。
町の決まりを確認してそろえよう!
町によっては、正装でなければ参加できなかったり祭り衣装の色に指定があったりするところもあります。何が必要か、あらかじめ確認しておくとよいですね。
もっと知りたい!浜松まつりQ&A
浜松まつりの参加にあたり気になる点をまとめました。細かいルールは町ごとに異なるので、事前に町の人に確認しましょう。

子どもが参加すると、親の参加も必要?

まつり当日は、子どもたちを見守る係の役員が町内にいますが、人数が多いと目が行き届かないこともあります。低学年までや子どもが慣れないうちは保護者も一緒に参加するほうが安心です。また高校生までは、21時までの帰宅が必須です。

自分が住んでいる以外の町でも出られる?

今住んでいる、実家や親の職場がある、知り合いがいるなど自分と縁のある町で、その町の法被とワッペンを手に入れることができれば参加できます。住人とそれ以外の人でワッペンの価格が異なる町もあります。

子ども会に入っていないと参加できない?

町によって異なります。まつりを取り仕切る主体が自治会という町もあれば自治会とは別の凧揚げ会という町もあり、子ども会とまつりの関係もさまざまです。

3日間とも参加しないといけないの?

一般参加なら、都合のつく日のみの参加でも問題ありません。子どもが小さいうちは体力的に大変なため、途中で休憩したり早めに帰ったりという人もいます。

衣装を全部そろえるのは大変。どうすればいい?

近所の人と貸し借りをしたり、リサイクルショップで探してみたりするのも一つの手ですね。町によっては法被を貸してくれるところもあるようです。
参加して楽しむ!浜松まつりの魅力
実際にどんなふうに参加したか、参加してみてどうだったか、市外から転入して浜松まつりに参加した2組に聞いてみました。
家族みんなの楽しみに
転勤族ですが、息子が友達に誘われたのをきっかけに「せっかくなら浜松でしかできない体験をしよう」と思い、参加しました。娘は4年生からお囃子もやっていますが、大人と一緒に盛り上がった「練り」にはまり、凧揚げにも毎年3日間とも参加しています。
私自身も練習の送迎や当番など大変ですが、当日を迎えると全部忘れるくらい楽しいから不思議。今まで地域との関わりがなかった夫も近所の人とお酒が飲めるのが楽しみのようで、家族みんなで毎年楽しんでいます。(5年生女の子、3年生男の子のママ)
地元じゃなくても大丈夫!
娘が4年生の時にクラスの友達から誘われてラッパ隊に参加しました。うちの町ではラッパ隊は3日間とも参加がルールなので、パパと交代で付き添っています。娘は友達と一緒に夜遅くまで集まっていられるのが楽しいようです。
まつりに参加したことで近所の人と深い交流ができるようになりました。地元じゃなくても皆さんやさしく受け入れてくれるので、転入して知り合いがいない人こそ、やってみてほしいです。(5年生女の子のママ)
取材を終えて
今回取材した皆さんが口をそろえて言っていたのは、浜松まつりは「見るより参加して楽しむまつり」であること、そして「地域の人と仲良くなれる」ということでした。浜松まつり会館の中村さんが「町の人はコミュニティを大事にするが、それは子どもに対しても同じ。同じ法被を着ていたら『うちの子』という感覚」と話していたのが印象的でした。地域の人に子どもの顔を覚えてもらえるのは、もしもの時の安心感にもつながりますね。子どもにとっても、同じ町内の子や大人と過ごす3日間は、特別な体験になるのではないでしょうか。
ぜひ家族で浜松まつりに参加して、地域の人と一緒に楽しんでみてくださいね。
取材・執筆/高田 まどか