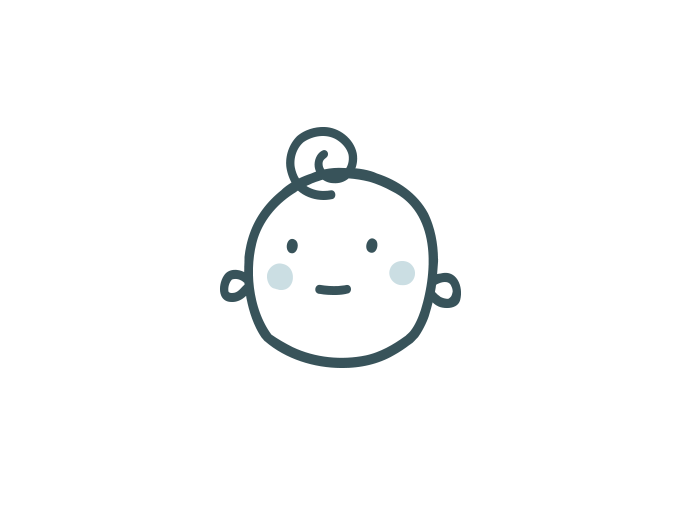平成27年度からスタートした子ども・子育て支援新制度では、保護者が認定こども園、幼稚園、保育園および地域型保育事業を利用するために、教育・保育の必要性に応じた教育・保育給付認定を受ける必要があります。
教育・保育給付認定は3つの認定区分(1・2・3号)に分かれ、認定区分によって利用できる施設や入園手続きが異なります。
注 従来型の私立幼稚園に通う場合は1号認定は不要です。
教育・保育給付認定区分
| 認定区分 | 対象者 | 利用できる施設 |
|---|---|---|
| 1号認定 | 子どもの年齢が満3歳以上で、教育を希望する場合 | 認定こども園(幼稚園機能)、浜松市立幼稚園、新制度の私立幼稚園 |
| 2号認定 | 子どもの年齢が満3歳以上で、保育を必要とする事由に該当する場合 | 認定こども園(保育所機能)、認可保育園 |
| 3号認定 | 子どもの年齢が満3歳未満で、保育を必要とする事由に該当する場合 | 認定こども園(保育所機能)、認可保育園、地域型保育事業、私立幼稚園(2歳児預かり) |
注 認定区分は満年齢、利用可能施設及び保育料は4月1日時点の年齢で決まります。
保育の必要量(2号認定・3号認定)
教育・保育給付認定で2号認定または3号認定を受ける子どもは、保護者の就労状況など保育を必要とする事由に応じて、「保育標準時間」と「保育短時間」とに区分され、利用できる時間が異なります。
| 区分 | 保育を利用できる時間 | 就労時間 ※保育を必要とする事由が就労の場合 |
|---|---|---|
| 保育標準時間 | 1日あたり最長11時間 | 保護者のどちらもが 月120時間以上 |
| 保育短時間 | 1日あたり最長8時間 | 保護者のどちらかが 月64時間以上120時間未満 |
注1 就労時間は目安で、就労以外の事由の場合も保護者の状況に応じて区分されます。
注2 標準時間・短時間の時間帯は施設ごとに異なります。時間外に利用する場合は延長保育となります。
施設等利用給付認定区分
| 認定区分 | 対象者 | 支給に係る施設・事業 |
|---|---|---|
| 新1号認定 | 子どもの年齢が満3歳以上で、保育を必要とする事由に該当しない場合 | 従来型の私立幼稚園 |
| 新2号認定 | 子どもの年齢が4月1日時点で満3歳以上で、保育を必要とする事由に該当する場合 | 認定こども園(幼稚園機能)、幼稚園、認可外保育施設、預かり保育事業、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業 |
| 新3号認定 | 子どもの年齢が4月1日時点で3歳未満で、保育を必要とする事由に該当し、かつ市民税非課税世帯である場合 |
注 幼稚園に満3歳で入園した新3号の子どもは、年少児から新2号に変わります。
保育を必要とする事由とは
2号認定、3号認定を受けるには、次の「保育を必要とする事由」に該当することが必要です。
| 保育を必要とする事由 | 保護者の状況 | 利用できる期間 (認定期間) |
|---|---|---|
| 就労 | 月64時間以上の就労(フルタイム・パートタイム・居宅内外労働) | 就労が継続している期間 |
| 妊娠・出産 | 母親が出産間近な状態、又は出産後間がない場合 | 出産予定日から起算して前8週間の月の1日から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日の月末 注)多胎児の場合は、出産予定日から起算して前14週間の月の1日から利用可能 |
| 疾病等・障がい | 保護者が疾病等で入院している場合や障がいを持っている場合 | 疾病等が回復するまで |
| 介護・看護 | 親族の介護・ 看護が常時必要である場合 | 介護・ 看護の必要がなくなるまで |
| 災害復旧 | 地震、火災、風水害等の災害復旧にあたっている場合 | 復旧が完了するまで |
| 求職活動 | 就労する意思があり、求職活動や起業準備に専念している場合 | 効力発生日から90日を経過する日の月末 |
| 就学・職業訓練 | 保護者が大学等に在学している場合や、職業能力開発施設等で職業訓練を受けている場合 | 卒業予定日・終了予定日の月末 |
| 児童虐待・DV | 児童虐待・DV を防止するために必要な場合 | 必要と認められる期間 |
| 育児休業 | 育児休業取得時に、すでに保育施設を利用している子どもがいて、継続利用が必要と認められる場合 | 育児休業取得期間(又はその月末) |
教育・保育給付認定の手続き
1号認定
入園の内定を受けた施設を通して、幼保支援課に認定の申請をします。
2号認定・3号認定
幼保支援課に、入園の申し込みと同時に認定の申請をします。
施設等利用給付認定の手続き
新1号認定・新2号認定・新3号認定
入園の内定を受けた施設を通して、幼保支援課に認定の申請をします。