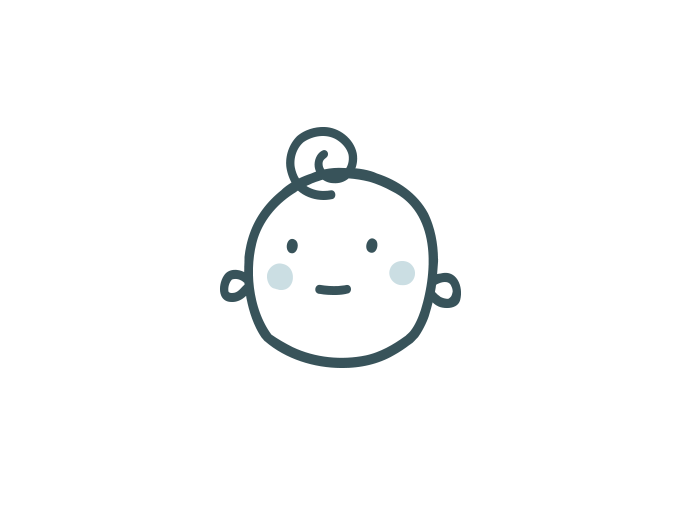子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
特集記事を検索
地域のつながりで守る「子どもの安全」
小学生になると登下校や放課後の遊びなど、子どもだけで出かけることが増えますね。その際親にとって心配なのが、子どもをターゲットにした犯罪です。静岡県警察によると、静岡県内の子どもへの声かけ等の不審者情報の届出件数は、年間1,000件を超えています。内訳を見ると小学生、なかでも中学年が、平日午後の下校時間帯(午後3時~6時)に多く被害にあっていることがわかります。(静岡県警察 令和6年不審者事案の発生状況より)
犯罪にあわないためにまずは子ども自身が防犯の知識や自分の身を守る方法を学び、普段から注意することが必要ですが、地域の協力も欠かせません。ここでは子どもを犯罪から守るための地域の取り組みについて紹介します。4月からの新生活に向けて、子どもと防犯について話し合ってみませんか。
知っておきたい「こども110番の家」
「こども110番の家」とは、子どもたちが危険や不審者等から緊急に避難できる地域の店舗や企業、一般の家庭のことです。子どもたちを不審者等から守り犯罪被害の未然防止を図ることを目的に、地域の人の協力を得て市内各所に設置されています。浜松市内には2024年末時点で約4,700件の登録があります。実際の運用は、警察や地域における青少年の健全育成や非行防止活動を行う市内48中学校区の青少年健全育成会と連携を取りながら行われています。
浜松市青少年育成センターの松島秀樹さんに浜松市のこども110番の家について詳しく聞きました。


こども110番の家の目印は?

登録された建物には、子どもたちが避難所として認識できるように、玄関口や店頭の見やすい位置にステッカーの掲示をお願いしています。青少年育成センターでも、子どもたちに広報活動として、便りやチラシ、出前講座などで、こども110番の家の周知に取り組んでいます。入学前に実際に親子で通学路を歩いてみることもあるかと思います。自宅付近や通学路を歩く際に、こども110番の家のステッカーを探してみてください。

どういう時に使えるの?どんな対応をしてもらえるの?

あやしい人に声をかけられた、車に乗ろうと誘われた、知らない人が後ろからついてきたなど、身の危険を感じた時や犯罪にあいそうになった時に、こども110番の家に助けを求めることができます。こども110番の家では、子どもが緊急避難をしてきた時、登録者に次の対応をお願いしています。
- 子どもの安全確保と身元確認、本人の話せる範囲での状況の聞き取り
- 110番、または最寄りの警察署に通報と保護者への連絡
- 警察、保護者が到着するまでの子どもの保護
- 対応終了後、青少年育成センターまで事後報告
プライバシーは守られます。危険を感じた時には、近くのお店やお家などに入って大人に助けを求めるよう、子どもに伝えてほしいです。

どんな人が登録しているの?

店舗や企業を中心に、個人で登録している人もいます。地域の自治会やPTA、青少年健全育成会の会員、民生・児童委員、育成指導員などにもご協力いただいています。「地域の子供は、地域で見守り育てる」を合言葉に、今後もこども110番の家への登録を呼びかけていきたいと考えています。

地域ごとの特徴的な取り組みはありますか?

地域の青少年健全育成会や学校により、独自の取り組みをされているところもあります。例えば、登録の事業所を記載した小学校区内のマップを独自に作成・配布したり、個人宅でもこども110番の家のステッカーを掲示しやすいよう、塀から吊れるプレートを作成・利用してもらったりしている地域もあります。

いきなり知らない人の家やお店に入るのは勇気がいりますよね。普段心掛けておくといいことは?

登録者には、子どもが緊急避難しやすい環境づくりとして、普段から地域の子どもたちとコミュニケーションをとることをお願いしています。子どもたちもあいさつなどで、地域の人とお互いに顔見知りになっておくと利用しやすくなると思います。地域全体で子どもたちを見守っている雰囲気は、犯罪者心理から見ても防犯効果が高いと言われています。
地域で見守る、子どもの安全
浜松市内には、地域ぐるみで防犯や交通安全活動に取り組んでいる地区があり、子どもたちの登下校時に、保護者以外で自主的に旗振り活動や声かけをしている地域の方もいます。
中央区三方原町では、浜松市全体でこども110番の家制度が始まる前から「子どもきんきゅうひなんじょ」の取り組みを続けてきました。その他にも、約40人の地域住民が通学時間帯の旗振り活動を行い、子どもたちの安全を見守っています。

この活動に長年携わっているのが、町内の「スーパーリフォーム石川」で洋服仕立て直し業を営む、石川篤さんです。
見守り活動を始めたきっかけは、20~30年前に自治会の役員をしたことだと言う石川さん。「下校時に体の小さい1年生が1人で歩いているのを見ると、かわいいと思う反面心配になりますよね。治安のいい日本ならではで、外国だったら連れ去られてしまうのではないかと思ってしまいます。遠くから歩いてくる姿をみると、心配でなにかしてあげたくなったからです」と話します。
石川さんも「子どもきんきゅうひなんじょ」の登録をしており、お店の窓ガラスにはステッカーが貼られています。実際に子どもが駆け込んできたことはないですが、このステッカーを貼ることで「昼間地域にいる大人で子どもたちを見守っている」という雰囲気づくりができると感じているそうです。

旗振り活動では、10年程前から毎朝、子どもたちの登校時間に合わせて車通りの多い横断歩道に立っています。蛍光イエローの帽子とユニフォームで横断旗を持つ石川さんの姿は、遠くからでもよく目立ちます。
さらに不審者の声かけなどの犯罪防止を目的とする、警察との取り組み「青色防犯パトロール」にも参加しています。週に一度、子どもたちの下校時間に、青色回転灯を装着した車で地域をパトロールしており、車の中の石川さんを見つけて手を振ってくれる子どももいるのだそうです。
長年子どもの見守り活動を続ける石川さんですが、2、3年前のそんなある朝のこと、毎日旗振りをしている場所を通る小学6年生の女の子が「いつもありがとうございます」と修学旅行のお土産をくれたことがあると嬉しそうに話してくれました。毎朝15人ほどの小学生が通る横断歩道で、今日も子どもたちにあいさつをしながら活動を続けています。
“子どもの安心”を育む地域のつながり
石川さんのように普段から継続的に行われている地域の防犯や交通安全の見守り活動によって、子どもたちがもしもの時でも気兼ねなく地域の大人に助けを求められる関係がうまれます。日ごろからのあいさつや声かけなどをきっかけに、地域の大人と子どもがお互いに顔見知りになりゆるやかにつながっていることは、子どもを犯罪から守るためにも大切です。
取材を終えて
取材したそれぞれの取り組みを通して、“地域で子どもたちを見守っていきたい”という大人たちの強い想いを感じました。小学生の子どもを持つ親のひとりである私も、身近な場所での見守り活動やこども110番の家の地域の方々への感謝の気持ちを持ちながら、何気ない子どもたちとの交流を大切にしていきたいです。そして、子どもが安心できる地域づくりが今後も広がってほしいと思いました。
取材・文/鈴木 とわ