子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
特集記事を検索
これでマスター!はじめてのなわとびチャレンジ

なわとびは、幼稚園や保育園で始める子も多く、小学校の体育でも毎年取り組むおなじみの種目ですね。子どもの運動能力の向上や体力づくりにもとても役に立つ全身運動ですが、「縄を回す」と「跳ぶ」の2つの動作をタイミング良く行うため、初めて挑戦する子にとっては難しいと感じることも少なくありません。家庭で練習する場合、どういう順序で練習するのがいいのか、コツをどう伝えれば子どもにわかりやすいのかなど、パパやママにとって悩ましいですね。
今回は、親子で楽しみながら取り組める練習方法やサポートのコツをプロに教えてもらいました。親子で一緒に、なわとびに挑戦してみませんか。
なわとびの基本、前とびにチャレンジ!
挑戦するのは平野さんと年長のじゅびちゃん親子です。じゅびちゃんは1回だけなら跳ぶことができます。しかし縄を腕全体で大きく回して、着地する時にかかとが地面についてしまい、連続跳びができません。
そこで、幼児・小学生を対象とした運動教室を行っている浜松アリーナ館長の山本昌辰さんに親子で楽しく練習するコツを教えてもらいました。
ジャンプゲームで準備運動
なわとびが跳べるようになるには、リズムよくジャンプしたり縄を回したりできることが大切です。そこで、まずはパパやママのかけ声や動きに合わせて跳ぶジャンプゲームで、楽しく頭と体をほぐしておきましょう。
命令ジャンプ
まず親子で向かい合って立ちます。パパやママが「前」「後ろ」「左」「右」と方向を言った後、子どもはその方向へジャンプします。
それができるようになったら、例えば「前」と言われたら「後ろに跳ぶ」といったように、言葉と逆の方向へジャンプしてみましょう。親子で手をつないで横に並び、一緒にジャンプしてもいいです。
グーパージャンプ
パパママは床に座り足を開いて、子どもは足の間に立ちます。足を閉じたり開いたりする動きに合わせて、子どもはその場でジャンプします。足を左右に開いたり足を閉じたりして着地しましょう。
最初は親子で手をつないで、慣れてきたら手を離して行ってもいいです。
なわとびの動作を分けた3ステップ練習
いきなり縄を持って跳び始めるのはちょっと待って!やみくもに跳び続けても、疲れるだけで子どもが嫌になってしまうかもしれません。楽しく効果的に練習するためにも、なわとびを動作ごとに分けて、ステップごとのコツをつかみましょう。
 跳ぶ つま先で跳ぼう
跳ぶ つま先で跳ぼう

なわとびは、リズムよくつま先で真上に跳ぶことが大切です。
まずは、足のマークやテープなどで跳ぶ位置に目印をつけて、同じ場所・同じリズムで続けてジャンプできるようにしましょう。
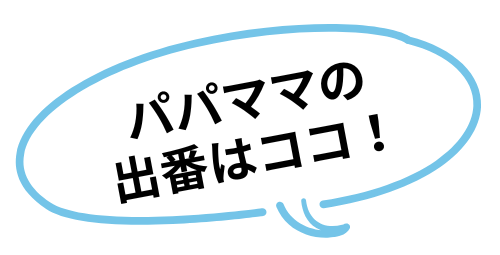
子どもだけでなく、パパやママも一緒にやってみましょう。手拍子やかけ声で子どもがリズムよく跳べるようにサポートします。その際「足はつま先だけ着いて、音が鳴らないようにジャンプできるかな」と声をかけてあげてください。何度も跳ぶことで、かかとを着けずにつま先だけで跳んで着地するなわとびの感覚をつかみやすくなります。
 縄を回す 腕を下ろして手で小さく回そう
縄を回す 腕を下ろして手で小さく回そう

連続して跳べるようになるためには、縄を腕全体で肩から大きく回すのではなく、腕を下ろしたまま手は腰のあたりで上下に動かすようにして小さく回すことが必要です。
まずは、親子で並んでひとつの縄を片手ずつ持ち、一緒に前に回します。慣れてきたら、回した縄が地面に着くときに縄の横でジャンプしてみましょう。跳ぶタイミングをつかむ練習にもつながります。
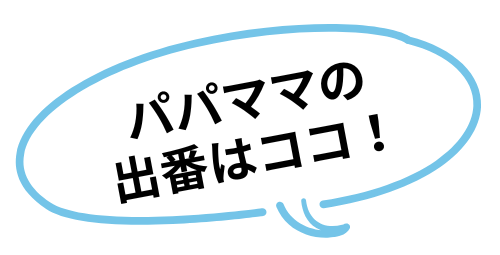
「手だけで小さく回せるようになると、交差とびや二重とびもできるようになるよ」と言って、実際になわとびをやってみせてあげましょう。いい刺激になって、子どものやる気もアップしますよ。
 縄を回して跳ぶ 前とびをしてみよう
縄を回して跳ぶ 前とびをしてみよう

いよいよ「跳ぶ」と「縄を回す」の動作を同時に行います。STEP1とSTEP2で紹介したジャンプや縄の回し方のコツを意識して跳んでみましょう。
最初のうちは、体の後ろから縄を回すことを理解できない子どももいます。回し始めやジャンプの時に合図をしてあげると、縄を跳ぶタイミングをつかみやすくなります。
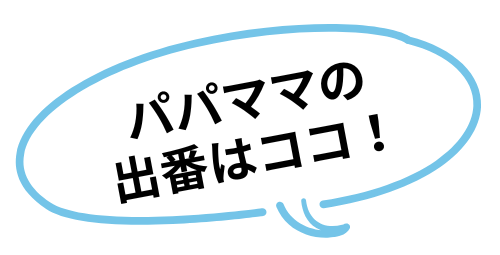
親子2人で前とびをしてみましょう。子どもを前にしてパパやママは後ろに立ち、1つの縄を一緒に持って跳びます。縄がこわいという子でも、親子で一緒に縄を持って跳ぶことで、安心して跳びやすくなります。また縄が下にきたタイミングに合わせて真上に跳ぶ練習にもなります。
先生からのアドバイス

〈Point1〉縄の長さと素材をチェック!
縄の長さは、縄を片足で踏んで持ち手が脇(胸の高さ)にくるくらいに調整しましょう。
二重とびなどの技をする時には軽いビニール製のものがいいですが、まだ力の弱い幼児が前とびを練習するときは、重さのあるロープタイプの縄のほうが、遠心力がついて回しやすいです。
〈Point2〉なわとび以外の遊びでもリズム感を養おう
なわとびは全身運動なので、始めたばかりの子どもには疲れやすい動きです。子どもの様子を見ながら無理なく練習しましょう。縄を使わない遊びもなわとびの上達につながります。準備運動で紹介したジャンプゲームやケンケンパ、グーチョキパーといった三拍子で足を動かす遊び、むすんでひらいてなどの手遊び歌も、親子でふれあいながらなわとびに必要なリズム感を養うことができます。
〈Point3〉焦らない!子どもと一緒に楽しもう
子どもがなわとびに挑戦する際、パパママは早くできるようにと焦ったり、他の子と比べたりせず、「跳ぶ」や「縄を回す」といった一つひとつのステップでできたことをほめてあげましょう。その子なりの成長を見守りながら、ぜひ親子でなわとびを楽しんでみてください。
親子で自主練習

先生の指導のあとも、楽しそうに何度もなわとびにチャレンジするじゅびちゃん。練習前と比べると、つま先でリズムよくジャンプできるようになり、1回1回の間隔も短くなっていました。連続とびができるまでもう少し!パパも「つま先でのジャンプなど、意識するポイントがよく分かりました。ほんの少しのトレーニングやきっかけでコツをつかんで、ジャンプの仕方にも目に見える変化があってびっくりしました」とうれしそうに話していました。
じゅびちゃんはその後も練習を続けています。縄をスムーズに回転させるまではあと一歩ですが、練習を始めて2週間で引っかからずに10回とべるようになったとのことです!
取材を終えて
平野さん親子には、遊びの要素を取り入れながら約1時間、なわとびに挑戦してもらいました。動作ごとのポイントを意識し、ステップアップしながら親子で一緒に練習することで、遊びを通じて自然に上達できることが分かりました。なわとびは子どもの成長を実感できるうえ、体力づくりにもつながります。ぜひご家庭でも、親子で楽しく挑戦してみてはいかがでしょうか。
取材・執筆/鈴木 とわ
取材協力:浜松アリーナ




