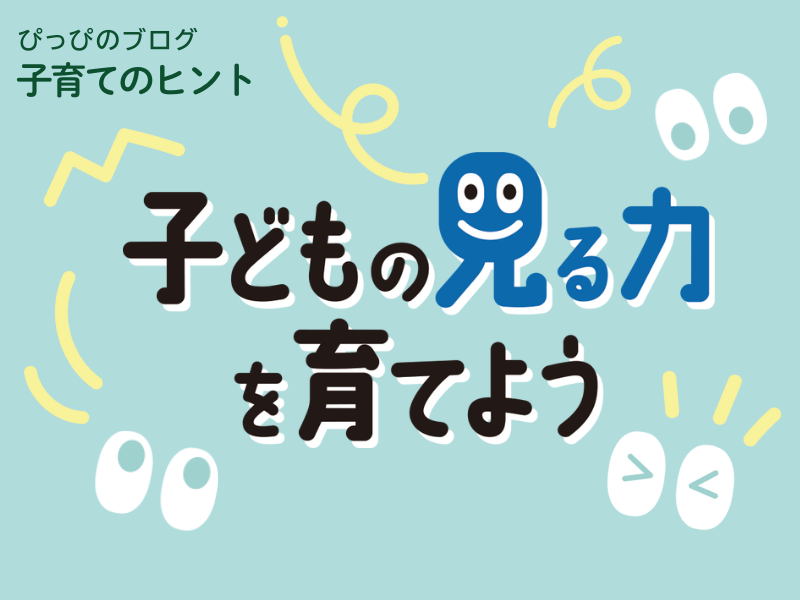子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
子育てのヒントを検索
災害への備えと対応
東日本大震災発災から2年半以上が経過しました。その間にも伊豆大島や竜巻など各地で様々な災害が起きています。災害の度、私たちは防災についての意識は高まっているのでしょうか?
先日掲載された朝日新聞世論調査では、自身の「災害への備えは不十分」89%という結果が出ています。今年、一般社団法人経済広報センターが行った「災害への備えと対応に関するアンケート」でも同様に3人に2人が自身の災害への備えは「不十分」と認識しているという結果がでています。

そうはいっても、人々は3日分程度の「食料、飲料水の備蓄」「非常用品の準備」(懐中電灯、電池、医薬品、ラジオ、靴、頭巾、ヘルメットなどのうち必要と判断したもの)、「日用品の備蓄(ティッシュ・トイレットペーパー、ごみ袋、ポリタンク、灯油など)」は準備しているのです。(南海トラフ巨大地震に備えるとなると1週間の備蓄と言われるのですが、そこまでの備蓄はされていないというのが現状のようです。)
もっとも興味深いのは
防災意識を「持続している(東日本大震災前から防災を意識し、持続している/東日本大震災をきっかけに防災意識は高まり、現在も持続している)」人が、どのようにして防災意識を持続しているかについてです。
「テレビや新聞、ラジオなどで防災情報を確認」が圧倒的に多く、続いて「防災用品や備蓄品などを定期的に確認」、「防災用品を常に見える所に置く」となっていました。東日本大震災が起きたときに、最も情報を得ていたのは、テレビ、ラジオ、新聞でした。信頼性が重要視されていたようですが、日常的に見聞きするという環境は重要なのかもしれません。

企業はというと、一般社団法人経済広報センターが行った「災害への備えと対応に関するアンケート」では、東日本大震災後、企業の備え(危機管理対策、事業継続計画など)は進んだと思うかについては、「進んだ」が10%、「どちらかというと進んだ」が49%で、合わせて59%が「進んだ」と回答されています。このように、決してこれまでの災害が私たちの防災への対処につながっていないわけではありません。しかし、意識は残念ながら薄れていきはじめているようです。
今後、「喉元過ぎれば熱さ忘れる」ものとならないためにも、防災に関する
- メディアからの定期的かつ効果的な情報発信
- ふだんの備蓄用品のモデルの顕在化
- 防災訓練の参加率を高める工夫
は継続的に必要なのではないでしょうか。
【参考】
・災害への備えと対応に関するアンケート(一般社団法人経済広報センター 、2013/11/26)
・朝日新聞社世論調査 (2013-11-25)