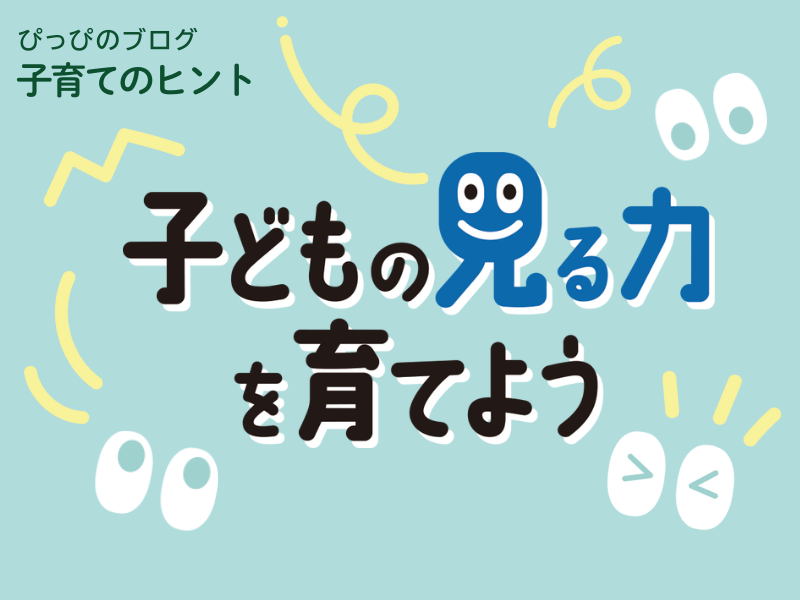子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
子育てのヒントを検索
耳の不自由な人が被災したら
少し前に(平成22年1月)NHKテレビ「ろうを生きる難聴を生きる」で、聴覚障がいをもつ方の阪神淡路大震災体験について取り上げていました。災害時や被災後は、聴覚に障がいがあるとコミュニケーションが大きな問題となり、それがただちに生命の危機につながります。たとえば、がれきの下になっていて、「誰かいますか?」「大丈夫ですか?」と呼ばれても、それが聞こえないのだから答えることもできません。食事や物資の配給のアナウンスがあっても、聞こえなければ受け取ることもできません。こうした予測される事態以外にも、さまざまな困難が起こるでしょう。
聴覚障がいは、一見したところ不自由さが見えないという点が、周囲から理解や援助を得づらくさせているという問題があります。静岡県聴覚障害者情報センターが発行する「聴覚障害者のための防災マニュアル」では、聴覚障がいの方への指導として「避難所生活では、『聞こえない』ことをまわりに伝えます」「地区の役員や消防団員の指示がわからない時には、遠慮なく聞くことが大切です」とあります。蛍光色の黄色い布に「耳が聞こえません」と書いたゼッケンや、「耳が不自由です お手数ですが筆記してください」と書いた名札などの写真が例示されています。
ボランティアの中には手話が出来る方や要約筆記のできる方もおられるでしょうが、そんな方たちがすぐに来られるとも限りません。そのため、聴覚障がいのある方には災害持ち出し品として、そうした表示グッズや筆記用品が必要でしょう。同時に、近所や知り合いで聴覚障がいのある方のことは平素から心にとめておき、必要な時に必要なサポートができるようでありたいと思います。
(ずきんちゃん)