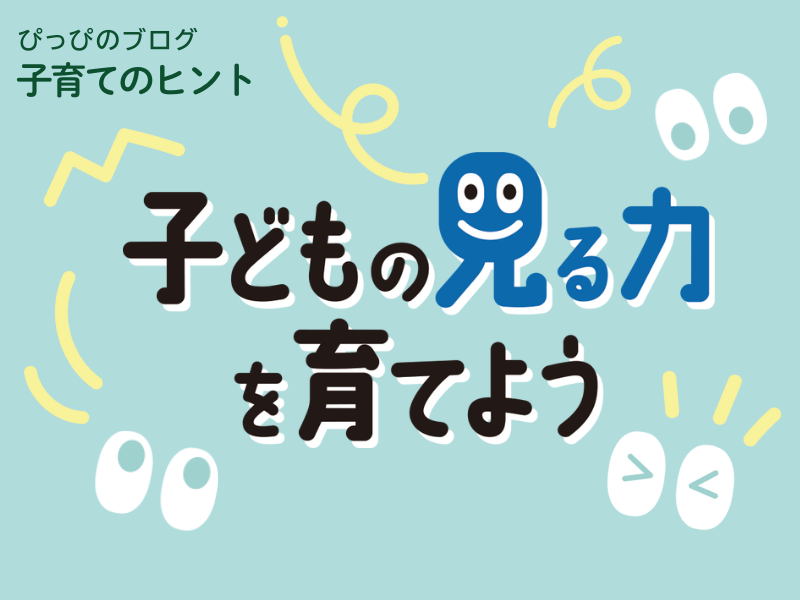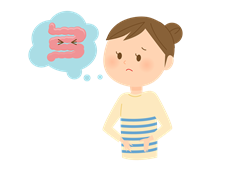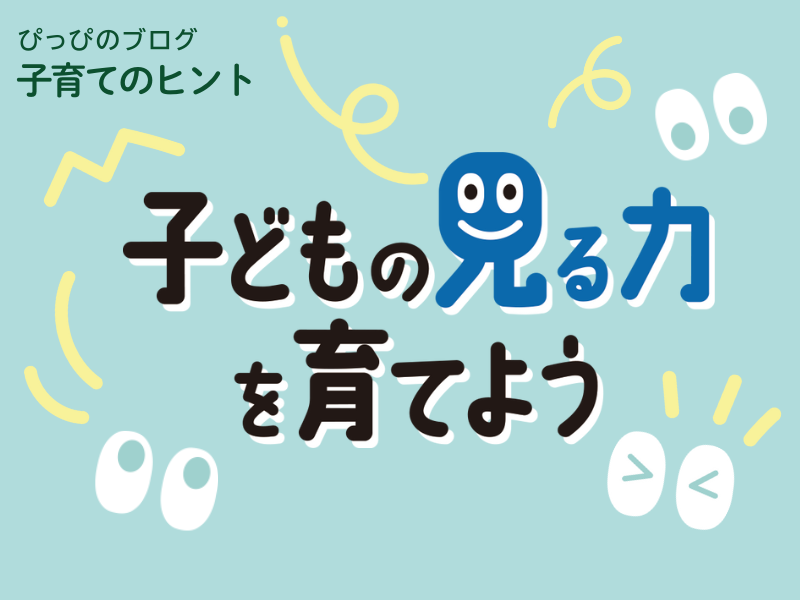子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
子育てのヒントを検索
子どもの見る力を育てよう(1)~見る力って、どういうこと??~

はじめに
私たちは毎日の生活で、たくさんの情報を見て、聞いて、感じながら行動していますよね。その中でも、実は「見る」ことから得る情報が約80%を占めているんです。でも、「見る」ことは普段無意識に行っているので、お子さんに何か困りごとがあっても、周りの大人が気づきにくいことがあります。
小学校に入って読み書きが始まってから、「あれ?」と思うことが多いのも、この「見る力」が関係しているかもしれません。
「見る力」って何だろう?
「見る力」というと、視力検査のことを思い浮かべる方も多いでしょう。もちろん、はっきり見えることも大切ですが、それだけではないんです。
例えば、テレビのリモコンを取りたいとき、お子さんはどんなことをしているでしょうか?
- リモコンを探す
- どこにあるか分かる
- 手を伸ばせば届くか判断する
- 実際に取りに行く
このように、「見えた!」で終わりではなく、見た情報をもとに行動することが「見る力」なんです。
日常生活での「見る力」
ボール遊びのとき
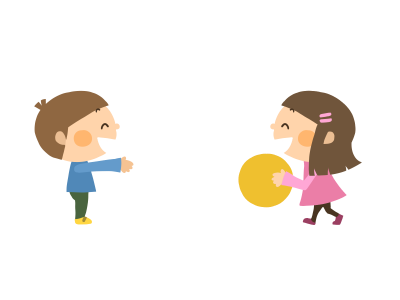
飛んでくるボールをキャッチするには、両目でボールを追いかけながら、距離感をつかむ必要があります。ボールを怖がるお子さんは、もしかしたらここに難しさがあるのかもしれません。
本を読むとき
文字を読むときは、近い距離にピントを合わせて、左から右、上から下へと目をスムーズに動かします。絵を見てから文字に戻るときは、どこを読んでいたか覚えておくことも必要です。
折り紙をするとき
先生の手元を見て、今度は自分の手元を見る。遠くから近くへ、素早く目を動かしながらピント合わせをしています。
方向感覚をつかむとき
「あっち」「こっち」の理解や、道順を覚えることも「見る力」と関係があります。自分の位置と周りの関係を理解する大切な力です。
絵を描くとき
見本の形を背景と区別して、全体を見て、部分も見て、それを紙に描く。見た情報を記憶して、手の動きにつなげています。
「見る力」はどうやって育つの?
「見る力」は生まれつき備わっているものではありません。赤ちゃんの頃から、いろいろなものに触れて、体を動かして、周りの人に支えられながら、日常生活や遊びの中で少しずつ身についていきます。
もし「見る力」につまずきがあると、成長とともに生活の中でちょっとした困りごとが出てくることがあります。
こんなサインに気をつけて!
よくつまずく

両目がうまく使えていなかったり、足元の段差に気づくのが苦手だったりすることが考えられます。
ボタンがけや靴ひもが苦手
ボタンの穴を見て、そこに向かって手を動かす「目と手の協応」が苦手かもしれません。
物や人にぶつかることが多い
自分の体の大きさや、相手との距離感をつかむのが苦手なことが考えられます。
大切なこと
「見る力」に問題があると、上手くいかないことが続いて、お子さんが自信を失ったり、イライラしたりすることがあります。周りの大人も気づきにくい問題だからこそ、お子さんへのプレッシャーが強くなってしまうことも。
小学校に入って勉強が始まると、読み書きの困難として表れることもあります。だからこそ、早めに気づいて、お子さんを支えてあげたいですね。
次回は、「見る力」を支える脳の働きについて、もう少し詳しくお話しします。