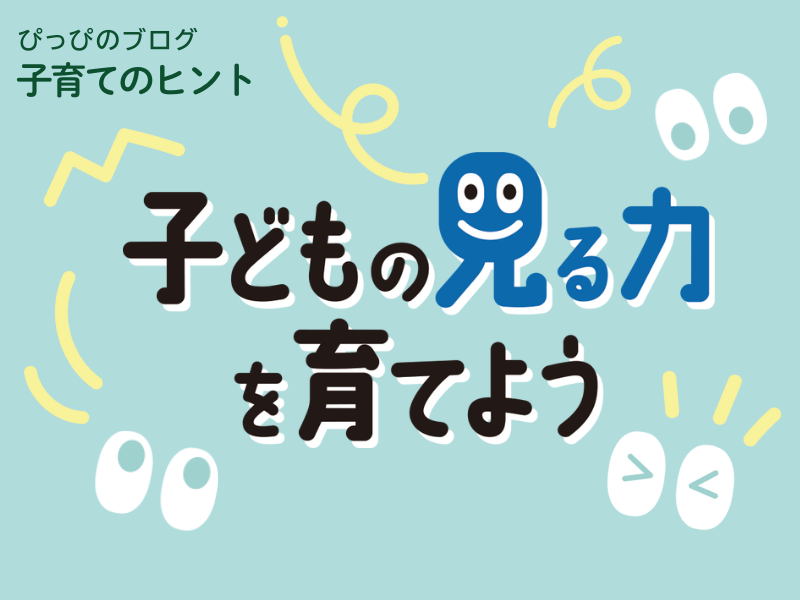子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
子育てのヒントを検索
怖い家屋の倒壊
14年前の1月17日早朝、ものすごい揺れを感じて目を覚ました。その時私は、神戸や大阪にいたのではなく、浜松にいました。その後、テレビをつけるとどこかの街中に火災が発生していて、ヘリコプターか何かの空からの映像には、何か所も大きな火柱や煙が映っていました。よく見ると建物も倒れているところもあるようで、どこに何が起こっているのか、現実なのかそれとも何かの映画かCMなのか、理解できませんでした。この恐ろしい景色が現実のものであり、被害が大きすぎて救急車や消防車が火災現場にたどり着くことすら難しいということが理解できたのは、ずいぶん時間がたってからだったと思います。
震災の後、テレビで行方不明者や亡くなった方の氏名、人数が放送されるのを見ながら、どこか現実的に思えなかったことや、そう思う一方、神戸に住む友人家族が無事なのかどうか心配でした。電話がなかなかつながらない状況ということだったので、数日後に電話をかけて無事を確認できるまでずっと不安を感じていました。
この記憶を、毎年この日が近づくと思い出します。
そして、昨年神戸の「人と防災未来センター」に出かけた時に、体験者でもあるボランティアの方から、当時の話を聞いた時、一番恐ろしいなと思ったことは、津波と家屋の倒壊でした。
特に、阪神淡路大震災の時の死者の8割が家屋の倒壊による圧死でなくなっているということに驚きました。ボランティアの方は、
「家が2階建てなら、1階には寝ない方がいい。」
とおっしゃっていました。10階建てのマンションも、3階と4階部分が2階の大きな音と振動とともにつぶれてしまい、8階建てのようになってしまったという話も聞きました。
最近では、耐震診断ができ、それぞれ耐震のための工事や立て直しなどを行っているお宅も多いのですが、まだというお宅は、ぜひとも耐震診断を行って、補強など必要な手立てをしてほしいと思います。
家屋の倒壊が恐ろしいと思った理由は、その死亡率の高さという数字的なものだけではありません。この「人と防災未来センター」では、当時の実話をもとに映像で大震災の時の状況を学べるようになっています。その中で、大きな揺れで家屋が倒壊し、二人の姉妹のうち、妹は近所の人に助け出されたのですが、姉を助け出す前に、近所の火災の炎が近づき救出を続けるのは危険と誰もが感じていた時に、
「いいから、逃げて!!」
と姉が言ったので、全員が救出を諦めたというシーンがありました。
もしも自分の家族や大切な人たちの中にこのようなことが起きたらと想像しただけで、胸が苦しくなりました。
家屋が倒壊しないようにするだけでなく、家具の下敷きにならないように、防災グッズなどを使って、もしもに備えましょう。阪神淡路大震災の時には、ピアノやテレビなどが水平に飛んできたということも言われていますので、家具が倒れないようにするだけでなく、テレビやピアノなどの重くて動きそうにないものでも転倒防止板などを使って対策しましょう。
実際、家にいる時に地震で揺れると、小学生などは学校の防災訓練などでやっている「机の下に潜る」という行動をとれるのですが、大人の方は案外何もできないという話をよく聞きます。しかしこれが、最も大切なことです。幼児などの小さい子どもたちには、揺れたら机の下に潜るということが難しかったら、
「団子虫になって!!」
といい、団子虫のように背中を丸めて頭を守る格好をあらかじめ教えてあげてください。
また、揺れた時にすぐに火の元を閉めるということはできそうでできない上に、もしも食事の準備などで火を使っている時に、無理に火を消そうとするとかえってやけどなどのけがをしてしまうことにもなります。最近のガス器具などは、揺れると火が消える仕組みになっているものが多いので、地震発生で無理に火を消そうとするのではなく、むしろ、やけどなどをしないように火から逃げることが大切なのです。
そして、一番にやらないといけないのは、命を守るために机などの下に潜り、頭を守ることなのです。
命がなければ子どもも家族も近所の人も助けることはできません。誰かを助ける・守るためには、まず、自分が助かることが大切なのです。