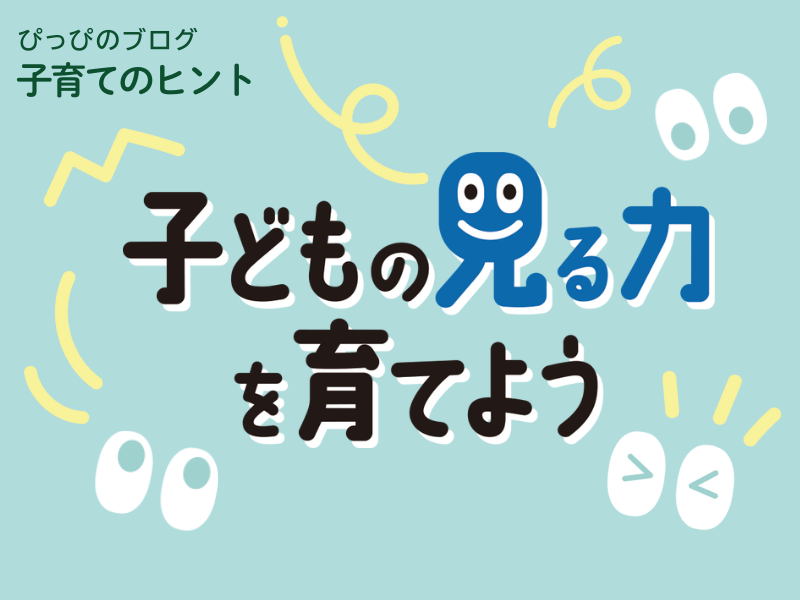子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
子育てのヒントを検索
阪神淡路大震災から15年
1月17日には様々なイベントが催されたり、特集番組が放映されていましたね。
神戸大学建築科の学生達が主体となった「震災犠牲者聞き語り調査会」の活動がTVで紹介されていました。
震災で亡くなった方々がどのように亡くなったかを遺族の方々に語ってもらい、当時の家の間取り図、故人の写真・エピソードなどとともにまとめ上げたものを冊子にして遺族に渡すというものです。故人のデータが形として残ることは遺族としても嬉しいし、多くのデータが残る事が供養になるのでなないかということで、1998年から取り組んでいるそうです。
当初年間100人ほどの調査をしていましたが、最近では数が減り、今までに361人の記録が残っています。調査隊が震災の記憶がない世代になってきていたり、今さら語るということについて遺族はどう考えているのだろうかという疑問など課題はあるようです。継続することは本当に大変なことだと思いますが、調査隊が震災を経験していない世代になっても(だからこそ)遺族の方々の語りを聞きとり、そこに生きていた証を残し震災の事実を伝え続けていってほしいと思ました。
また、震災直後に結成された「神戸大学学生震災救援隊」が今でも活動を続けているという記事(静岡新聞1月7日付)を見つけました。
元々は家屋の片付けや炊き出しの手伝いをしていましたが、その後、神戸の町を歩き、震災時の様子を学びながら、復興住宅での「お茶会」をはじめ、能登、中越の被災地での「足湯サービス」、ホームレスへの支援など多彩な活動となっています。「人と町にかかわり、支える」という思いをつなげ続けているということでした。
さて、ハイチ大地震では食料を我先にと奪い合う様子が報道され胸が痛む思いでしたが、1月20日、8日ぶりに2人の子どもが瓦礫の下から救出されました。しかしこれまでに約7万人の遺体が収容され、いまだ多くの人々が瓦礫の下に残っています。今必要なものは、水と食料、仮設住宅、瓦礫の撤去作業だそうですが、災害はいつ自分に降りかかってくるか分かりませんから、他人事とは思えません。
物質的な備えはできているか、日頃から近隣の方とのコミュニケーションがとれているか、自分に何ができるだろうか、自分自身に問う今日この頃です。