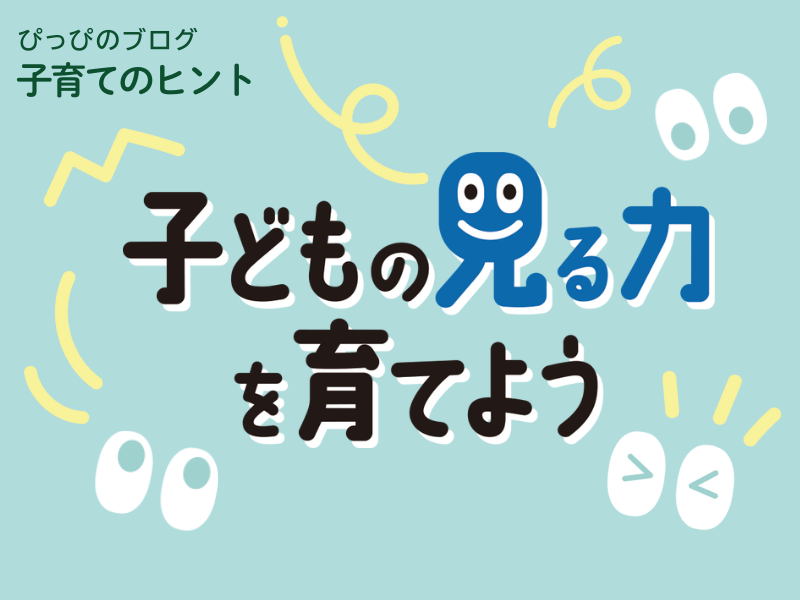子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
子育てのヒントを検索
災害支援にジェンダーの視点を
被災すれば、誰もがとても大変な思いをします。ですが、その中でも多様な人々がいて、特に弱い立場になる人々が存在します。
そうした脆弱(ぜいじゃく)性の高い人々、特に女性の権利が満たされる環境づくりを目指し、ジェンダーの視点をしっかりと取り入れた防災(復興)対策・体制を普及させていくことを目的に設立された組織があります。今年4月に設立された「減災と男女共同参画 研修推進センター」(東京都文京区)です。
この前身である「東日本大震災女性支援ネットワーク」が発行した『こんな支援が欲しかった!~現場に学ぶ、女性と多様なニーズに配慮した災害支援事例集』は、東日本大震災の支援活動にあたったさまざまな団体の経験から得られた支援事例を集めた冊子です。
事例の中には、乳幼児など小さい子どもをもつお母さんの負担・不安を軽減するために行われた支援の例が多数収録されています。例えば、被災地の過酷な環境から、赤ちゃんと家族を一時的に被災地外に避難させる「赤ちゃん一時避難プロジェクト」。また、避難所で小さい子どもを持つお母さんの手を空けるために、子どもの預け合いを行った例。
お母さんに限らず、女性には災害時、特有の危険や困難さが増します。帰宅困難に陥った女性のために、ツイッター等を通して情報を流し、安心して滞在できる場所を提供した例。また、女性を起点とした支援が必要との観点から、「女性支援センター」が設置された例もあります。
同冊子の前書きに、考え方を端的にまとめた文章があるので、一部抜粋します。「災害にあった方々は『被災者』と一括されがちですが、性別、性別自認、年齢、障がいの有無、国籍や母語の違い、家族構成や就労状況によって必要とされる支援は異なります。『多様なニーズに配慮した支援を行っていますか』という私たちの問いに、多くの皆さんは『専門の職員がいないからできない』とおっしゃいました。女性支援は女性団体、障害者支援は障害者団体、と感じておられるようですが、専門性を持った団体でないと、多様なニーズに応えられないのでしょうか?~中略~実際に災害が起きた時、すぐ現場で支援を始め、復興段階まで長期的に関わるのは、地域の組織・地方自治体・支援団体です。各地で専門の団体を待つよりも、だれもが多様性に配慮した支援ができるようにすることのほうが大切です」
◎『こんな支援が欲しかった!~現場に学ぶ、女性と多様なニーズに配慮した災害支援事例集』
冊子の内容がネットで閲覧することができます。(こちらのサイトからPDF版がダウンロードできます)

☆ずきんちゃん☆