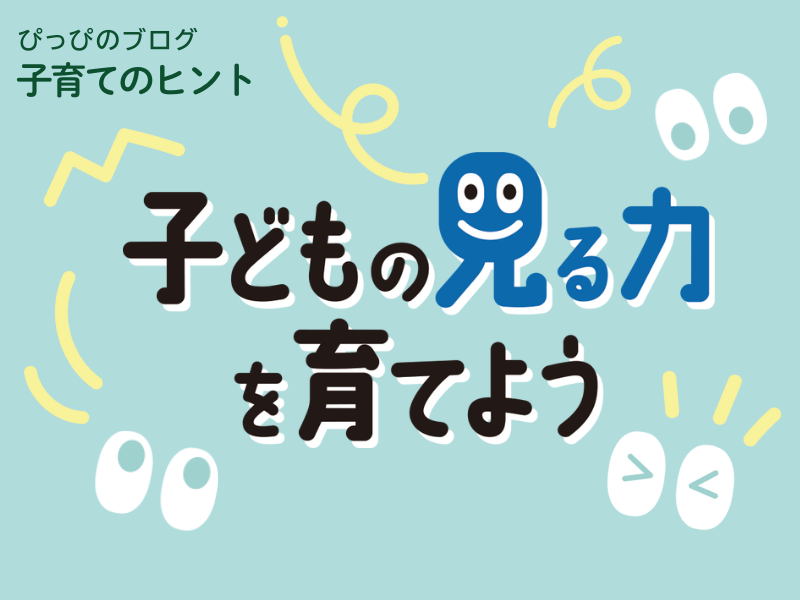子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
子育てのヒントを検索
アレルギー患者の災害時対応を考える
食品の摂取により発症する食物アレルギー患者の増加が社会問題にもなってきていますね。以前、乳製品にアレルギーがある小学生の女児が給食を食べた直後に死亡したというニュースは記憶に新しいですが、文科省が昨年の平成25年に調査した「学校生活における健康管理に関する調査」[1](アレルギー疾患部分に関して)調査対象児童生徒数合計 10,153,188 人(28,958 校)による結果報告から見ると、小学校から高等学校までの生徒で食物アレルギー疾患のり患者数は全国で453,962人ほどいると言われています。
近年、食物アレルギーも様々な食物に対してアレルギー反応を示すことがわかってきて、アレルギーに気づいていれば家族が注意するなど対処はできるのですが、まったくアレルギーと気づかないで調子が悪い、原因不明で扱われる場合もあるようです。
このような中で、災害時はとてもたいへんな状況に陥ることは明白です。もちろん備蓄は大切なことですが、アレルギー除去食品を常に持ち歩いているということは困難です。
もしも、災害に遭って避難所生活を強いられてしまったら?支援物資の中にアレルギー反応を起こしてしまう成分が含まれていたならば?アナフィラキシー反応を起こしてしまうかもしれません。自分がどんなアレルギーを持っているのかを把握しておくことは自分の命は自分で守るということにつながります。まずは検査をしておきましょう。
また、アレルギー対応のアルファー化米が備蓄してある自治体についてご存知でしょうか?アルファー化米備蓄をしている自治体についてはNPO法人アレルギー支援ネットワークのWebサイト[2]に掲載されています。これから見ても決して多くはありません。
“お住いの自治体に、アレルギー対応の食糧が備蓄されていない場合は、是非、備蓄の検討をしていただけるように要望をだしましょう>NPO法人アレルギー支援ネットワーク”
災害時、緊急の場合、どうしても備蓄品を持ち出せない場合もあります。こうした要望はいつ起こるかわからない災害と言えども生死にかかわることにもなりかねません。ぜひ、出されることをお勧めします。
参考:
[2]NPO法人アレルギー支援ネットワーク アルファー化米備蓄について
<hiro>