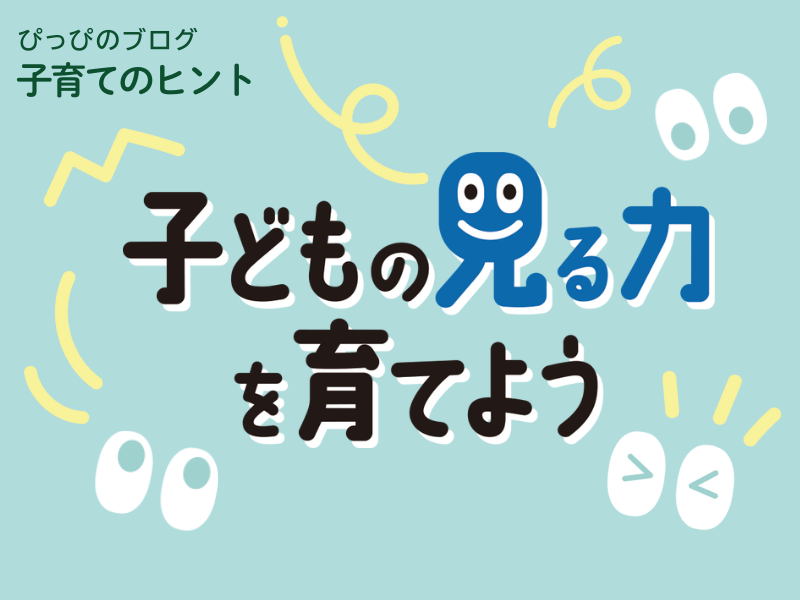子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
子育てのヒントを検索
身近な保存食
ハロウィンが終われば、次のお楽しみはクリスマス。クリスマスのお菓子と言えば、ドイツの伝統的なお菓子シュトーレン。

クリスマスを待ちながら、何週間も前から、薄くスライスして少しずついただきます。日持ちがするのは、ラム酒漬けにしたドライフルーツを大量に使用していること、溶かしバターを何度も塗り重ね、最後に全体に粉砂糖をたっぷりまぶしてコーティングするという作り方に秘密があります。伝統的な作り方の中に、長期保存のテクニックが組み込まれています。
日本にも長期保存が可能なお菓子があります。保存がきき、エネルギー補給にもぴったりで登山などの携帯食としても重宝なのか羊羹です。

羊羹は、小豆・砂糖・寒天を主原材料に、100℃を超える温度で長時間煉っているので微生物が発生しにくく、また砂糖の含有量が多く、微生物が増殖しにくいことから、品質の変化が少ないとされています。砂糖が食品の水分を抱え込み、カビや細菌などの微生物が必要とする水分を奪うからと言われています。ある和菓子メーカーでは、賞味期限を1年とし、賞味期限過ぎても1年間は安全だと公表しています。
さて、ご飯が余ると、ラップに包んで冷凍庫へ、再び食べる前にレンジでチンして・・・というのが今風ですが、昔は余ったご飯は水で軽く洗ってぬめりを取り、天日で乾燥させて保存食としていました。これが糒(ほしいい)でお湯や水でもどして食べます。いわゆるアルファー米に近いものになります。
弥生時代に米作りが始まって以来、保存食として存在し、飛鳥時代の倉庫令では糒の保存期間は20年と設定されていて、伊勢神宮の式年遷宮もこの保存期間が元となったという説もあります。その他、戦いや旅の携帯食として使われていましたが、大きな自然災害に見舞われている現代に、この保存力(?)が見直され注目されています。
風土の違いや温暖化の影響などで、乾燥の度合や保存可能期間等などが変わってくるかと思いますが、古代に思いをはせて保存食づくりにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
<やまねくん>