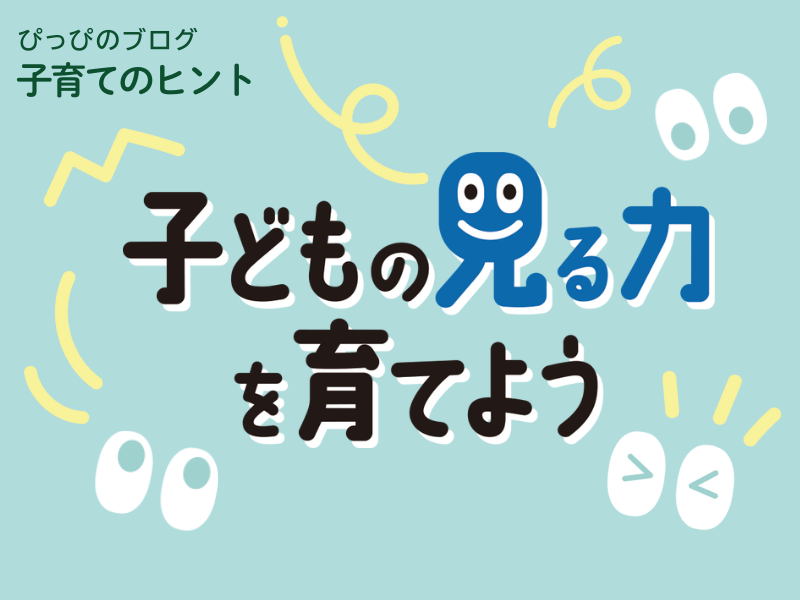子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
子育てのヒントを検索
ためこみ
保育用語で「ためこみ」は、一見何も活動をしていないように見える子どもが、周囲の環境(仲間の遊んでいる姿・方法)をどこかで見つめていて、自分の中に取り込む静の活動を行っていることを指して言います。 幼稚園に勤めていた頃、園庭のそこかしこで年長組の子どもたちが自分たちの遊びにうち興じるなか、年中・小の子どもたちは、お兄さん・お姉さんの遊びに全く興味などありませんという顔で自分たちの遊びに取り組んでいたのに、年長組の子どもたちが使っていた遊具に飽きて別の遊びをしだすと、そっとその遊具に寄って行って、年長組のお兄さん・お姉さんと同じ遊び方で(でも、同じようにはうまくできないのですが)、果敢に挑戦している姿を何度も見ることがありました。
幼稚園に勤めていた頃、園庭のそこかしこで年長組の子どもたちが自分たちの遊びにうち興じるなか、年中・小の子どもたちは、お兄さん・お姉さんの遊びに全く興味などありませんという顔で自分たちの遊びに取り組んでいたのに、年長組の子どもたちが使っていた遊具に飽きて別の遊びをしだすと、そっとその遊具に寄って行って、年長組のお兄さん・お姉さんと同じ遊び方で(でも、同じようにはうまくできないのですが)、果敢に挑戦している姿を何度も見ることがありました。
「ためこみ」は子ども同士の関係に留まらず、大人の姿をも子どもは「ためこみ」をしています。幼稚園でよく行われるお母さんごっこの場面で、お母さん役の子どもが、子ども役の子どもに小言を言う場面では、「あーこの子のお母さんは、こういう言い方をするんだな」と微笑ましく見ていることがあります。逆もしかりです。幼稚園ごっこや保育園ごっこで、先生口調そのままで話しているお子さんの姿を見られた方もきっとおられるでしょう。
子どもはいつも全身全霊で周りの全てを感じ取っています。
そして大人になった時に、今までためこんできたことを基軸に人間関係を折り成していきます。例えば、家庭の中で、笑いや温かさの中で育った子どもは、大人になった時、温かい家庭を自然に作り出そうとします。しかし、幼児期に虐待を受けていた子どもは、自分がためこんだ虐待を自分の子どもに向けざるを得ません。幼児期の「ためこみ」は、自分が好むと好まざるに関係なく生き方の基軸となってしまうのです。
だからこそ願うのですが、皆さんのそばにいる小さな瞳と今をゆったりと楽しんでほしいと。そうすれば、その小さな瞳が大きくなった時に、同じような眼差しで新たな小さな瞳に対して向き合っていくでしょう。