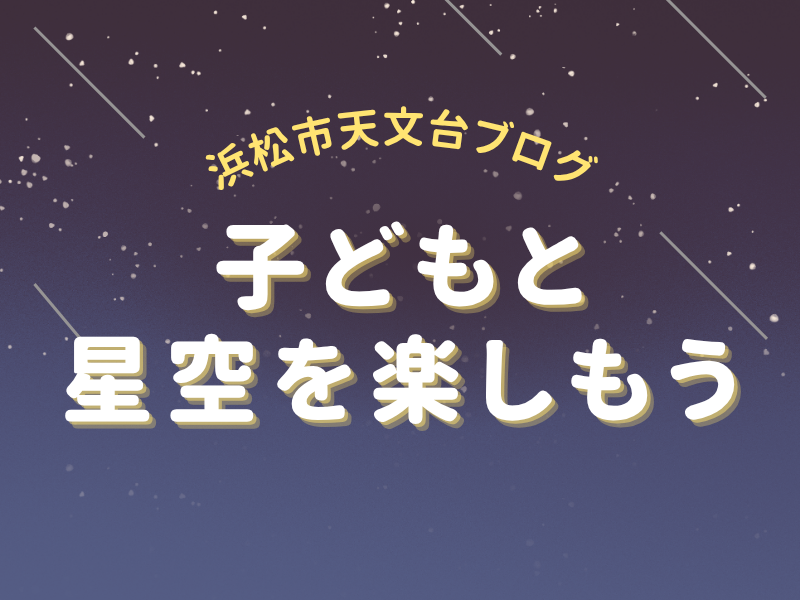子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
子育てのヒントを検索
子どもの見る力を育てよう(4)見る力と体の動き~お子さんの成長をサポートするために~

「見たもの」を「体の動き」に変える力
今回は、これまで説明したように、お子さんが目で見たもの「入力→情報処理」を実際に体を動かして行動する「出力機能」のお話です。頭ではわかっているけど、実際にやってみるって難しい。出力の機能が上手につながることで、初めて物事はうまくいくわけです。
たとえば、こんな日常の場面を思い浮かべてください。
- お絵描きのとき…鉛筆を手に取り、紙にペン先を適度な力で押し当てて、思った場所まで手先を動かす。
- ボール遊びのとき…飛んでくるボールをよく見て、ちょうど良いタイミングで手を握って捕まえる
- 着替えのとき…ボタンの穴を見ながら、両手を器用に動かしてボタンを留める。
これらすべてに、「目と体の連動」が必要なのです。
「できない」のは、見ていないから
お子さんが何度やってもうまくできないとき、つい「ちゃんと見なさい!」と言ってしまうことはありませんか?でも実は、お子さんは一生懸命見ているのです。
問題は、見た情報を頭の中でイメージに変換する力や、そのイメージ通りに体を動かす力がまだ育っている途中だということ。頭では「こうすればいい」とわかっていても、体がそう動いてくれない。お子さん自身も困っていて、「どうしてできないんだろう」と落ち込んでいるかもしれません。お母さんにできるサポートとして、そんなときは、見せるだけでなく、体験させてあげることが大切、ということです。
具体的なサポート方法は、
1. 手を添えて一緒に動かす
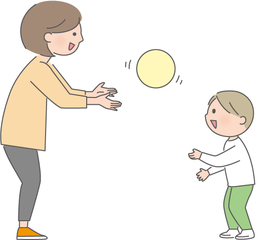
- ハサミの使い方を教えるときは、お子さんの手に自分の手を重ねて、開く・閉じるリズムを体感させてあげましょう。
- 文字を書く練習では、手を添えて「止める」「はらう」の感覚を一緒に味わいます。つい、付き添っている大人はうまく書かせようとしてピリッとしてしまいますが、体感させてあげることが目的ですので評価をしなくて大丈夫です。
2. ゆっくり、段階的に
- 「ボールを投げて」ではなく、まず「腕を後ろに引く→前に振る→手を離す」と分解して伝えましょう。
- 一つひとつの動きを確認しながら、焦らず進めましょう。
3. 感覚を言葉にする
- 「ぎゅっと握ってね」「ふわっと手を開いてね」など、動きを擬音語で表現すると、お子さんはイメージしやすくなります。オノマトペの共有は、のちの共感性を育てることにもつながります。
- 「ここまで力を入れるといいよ」と、力加減も丁寧に伝えましょう。
毎日の遊びが、子どもの「見る力」を育てる
大事なことは、毎日の遊びが「見る力」を育てる、ということです。「見る力」と「体を動かす力」は、特別な訓練ではなく、日々の遊びや生活の中で自然に育っていきます。
- 積み木やブロック遊び
- 粘土やお絵描き
- ボール遊びやかけっこ
- お手伝い(お皿を運ぶ、洗濯物をたたむなど)
これらすべてが、お子さんの「見る力」と「体の連動」を育てる貴重な経験です。できないことを叱るのではなく、小さな成長を一緒に喜ぶ。焦らず、その子のペースで見守る。お母さんの優しい声かけと手助けが、お子さんの力を確実に伸ばしていきます。
「見る力」は、さまざまな体験の積み重ねから獲得されるものです。 日々の生活の中での関わりが、お子さんの成長に大きな影響を与えていることを、心に留めておいていただけたらと思います。
お子さんの「できた!」という笑顔のために、今日からできることを一つずつ始めてみませんか?