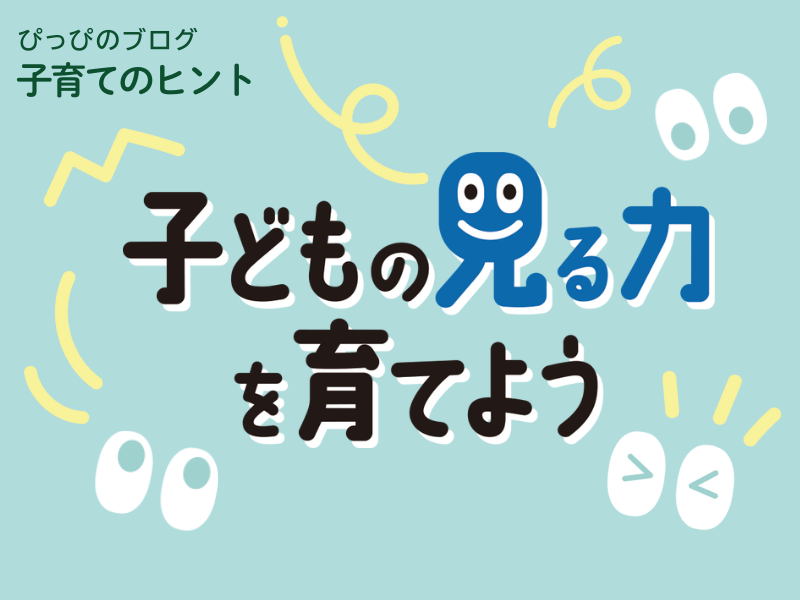子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
子育てのヒントを検索
「やさしい日本語」とは?
先日、「やさしい日本語」についての講演を聴く機会がありました。
1995年に発生した阪神大震災では、「震度」「避難所」「倒壊」などの普段聞き慣れない日本語が理解できず、避難ができなかったり、災害援助を受けられなかったりした外国人がいました。
私たちは、外国語として英語を習ってきましたが、すべての外国人が英語を理解できるわけではありません。浜松で生活している外国人も、ブラジルはポルトガル語、同じ南米でもペルーはスペイン語と母国語も様々です。かといって多言語への通訳や翻訳には時間と人手がかかります。
わかりやすい日本語を使うことで、聞く側、伝える側の双方にとって、スムーズな情報伝達の手段になるのではということで「やさしい日本語」が考え出されました。
「やさしい日本語」は、
日本語に不慣れな外国人にも、”簡単でわかりやすい日本語で”情報を伝えること。
それは、外国人だけでなく、日本人にとってもわかりやすいものとなるでしょう。
◆文の構造を、わかりやすくする。
・単文にする。文章を短くする。
・主語、述語、目的語の関係を明確にする。
◆言葉の語彙や漢字
・わかりにくい言葉は言い換える。
・漢字を少なくし、フリガナをつける。
言い換えの一例 災害時バージョン
=======================
安否 → 大丈夫かどうか
全壊 → 全部壊れた建物
貴重品 → 大切なもの、大事なもの
※よく使われ知っておいた方がいい言葉は、元の言葉も残し、言い換えた言葉を添える。
震度 → 震度<地震の大きさ>
津波 → 津波<高い波>
消防車 → 消防車<火を消す車>
避難所 → 避難所<逃げるところ>
=======================
なるほど! と思うものもありますね。
誰かに情報を伝える時には、状況、相手、伝えたい内容などによって、いろいろな手段があり、その場に応じて使い分けます。
その一つとして、やさしい日本語の考え方は、災害時のみならず、普段から意識しておきたいと思います。