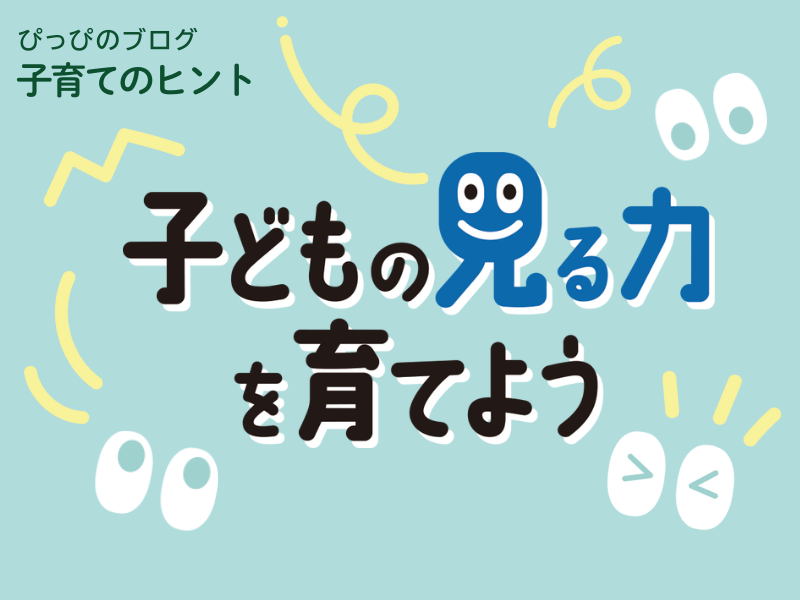子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
子育てのヒントを検索
世界津波の日
昨年、国連は、東日本大震災のあと日本で制定された「津波防災の日」の11月5日を、「世界津波の日」と定めました。
国連の新たな開発目標が自然災害の被害を減らすことを目指しており、各国が津波の早期警報システムなどを整備する重要性を強調し、今後は啓発活動などを取り組んでいくことになります。
東日本大震災は3月11日なのに、どうして11月5日なのかというと、「稲村の火」に由来します。
「稲村の火」というのは、嘉永7年11月5日(1854年12月23日)の実話からできたお話です。津波が紀伊半島から九州まで襲ったという「安政南海地震」の時に、紀伊国広村(現在の和歌山県有田郡広川町)の庄屋の浜口儀兵衛(梧陵)が機転をきかせ、収穫したばかりの稲に火をつけ、村人たちに火事が起きたと思わせて高台に避難させ、命を助けたというものです。
ここから、平成23年6月に「津波対策推進法」が成立した際、国民に津波対策について関心と理解を深めるために、11月5日を「津波防災の日」としていたのです。これを日本が国連に提案し、全会一致で採択されたのです。
東日本大震災後、まだまだ被災地では、元通りの生活に戻れていない地域や人たちがたくさんいます。「東日本大震災」という災害を、他人ごとではなく自分事として、これからも機会があるたびに思いだし、自分にできることを考えていきたいものです。
そのきっかけのひとつとして、「世界津波防災の日」を、みんなで津波防災について思いだし、備えるきっかけにできると良いですね。
(わかば)