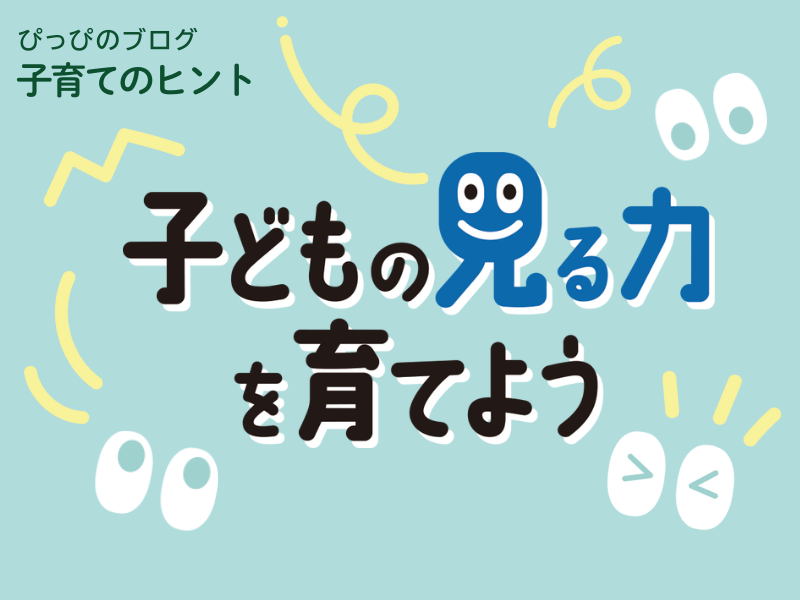子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
子育てのヒントを検索
『天災と日本人 〜地震・洪水・噴火の民俗学〜』
2011年に起こった東日本大震災は、私たちに津波の恐ろしさや大規模災害への備えを考えさせる大きなきっかけとなりました。だから東日本大震災以降は、「災害」といえば、「地震」「津波」がまず最初に頭に浮かぶようになったという人も多いのではないでしょうか。しかし、災害が多い日本では、災害とは、地震・津波だけではなく、風水害や火山の噴火なども無視することはできません。特に近年、集中豪雨やそれに伴う土砂災害などは、頻繁に起こっているといえるのではないでしょうか。
天災と日本人: 地震・洪水・噴火の民俗学 (ちくま新書 1237)
posted with amazlet at 18.12.05
畑中 章宏
筑摩書房
売り上げランキング: 97,391
筑摩書房
売り上げランキング: 97,391
この本には、2011年の東日本大震災だけでなく、2014年に起こった広島豪雨災害、御嶽山噴火、関東・甲信越・東北という広い範囲で記録的な大雪となった豪雪などを例に、その土地の歴史的・地理的な背景を含めて書かれています。私たちが作った「ぴっぴ家族の減災BOOK」では「昔からの言い伝えを知る」ことの大切さを紹介しているのですが、この本を読んでいると、さらに納得させられます。その一つに、昔の地名を調べると、その土地の特徴がわかるということがあります。例えば、昔「蛇崩(じゃほう)」という地名がついていたところは、土砂災害が起こりやすい土地につけられていたことが多いとか。
災害への備えとして、過去に起きた災害を知ることもそのひとつです。まずは、自分の住んでいるところが以前はなんという地名だったのかを調べてみるのはいかがでしょうか。
(わかば)