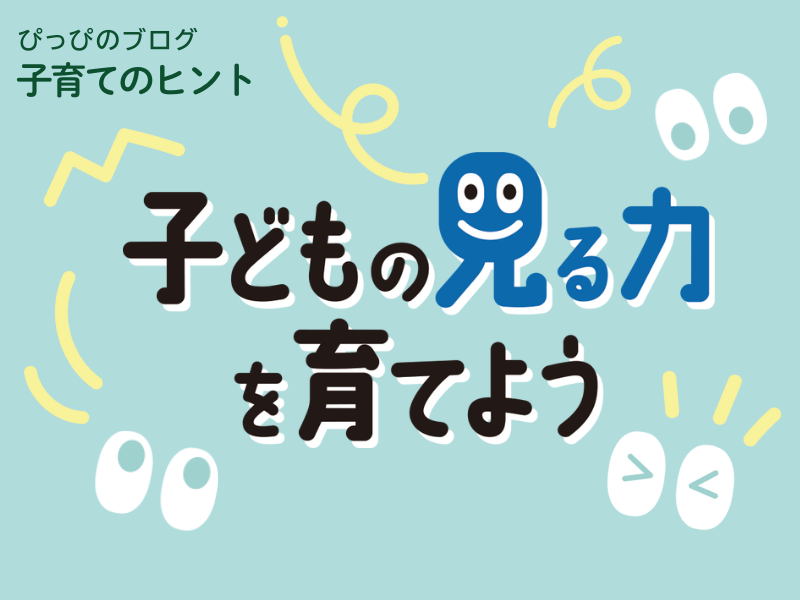子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
子育てのヒントを検索
ぴっぴの能登支援活動の振り返り
今年、1月1日に起きた能登半島地震以降、認定NPO法人はままつ子育てネットワークぴっぴ(以降、「ぴっぴ」)の珠洲市支援活動をもとに被災地における子どもの支援について考えてみました。
1月~2月
「ぴっぴ」は、珠洲市や珠洲市の人々が主に2次避難先としている金沢市にも、つながる支援パックを支援物資として必要分の数だけお送りしました。その後、リクエストがあり、幼児用の離乳食や下着などをお送りしました。
災害後の被災地はどんどんフェーズが変わってきます。もともと、珠洲市に限ると、上下水道がなかなか復旧せず、現時点でも水道復旧している地域は少ない状態です。その中で、乳幼児を育てるのはたいへんだということで発災直後から若い子育て世代の多くは珠洲市を後にしてしまっています。おそらく他の市町もそのような状況なのかもしれません。
災害後、インフラの復旧遅れもそうですが、若い子育て世代を含めた人々が失職してしまうと元の住居があったところに戻るのは困難になり、まちは人口が減って過疎化してしまいます。若い人々の手がないと活気もなくなり、未だ手付かずの片付けも進まず、それがさらに復興を遅らすことになり悪循環です。
3月
現状、2次避難先がホテルなど仮の場所であると、個別に生活用品をそろえなければならず、相当な出費となり、元の被災した住居が残っていれば戻る家庭もあるようです。
4月~

珠洲市は、小学生だけですと3つの小学校が再開し、200人ほどの子どもたちの通学が始まったと聞きます。仮設住宅もどんどん建設され、その中に集会場が作られています。子どもたちにとって学校や公園が仮設住宅等になってしまっているため、遊び場やモノが不足しているとのことでした。そこで、「ぴっぴ」では、絵本やおもちゃの寄付を募り、そして他事業で当団体がいただいた段ボールでできた卓球台とラケット・ボールセットを送りました。
これまでの活動を振り返りますと、乳幼児、特に幼児の離乳食やお菓子、下着などが不足していました。支援物資としてミルクやおむつは届いたそうですが、6、7か月以降の幼児に対するものは、おとなの食料をわければよいと考えがちですが発達に大きな影響を与えてしまうので配慮が必要です。
要配慮者のニーズは見過ごされてしまいがちです。他の人よりじぶんはまだ、ましだからと我慢するのではなく、「○○がなくて困っています」と伝えてもらえるほうが後の人々の支援にもなります。
今後、ぴっぴでもつながる支援パックの内容について検討していくことにします。
文/浜松市防災学習センター 副センター長 原田