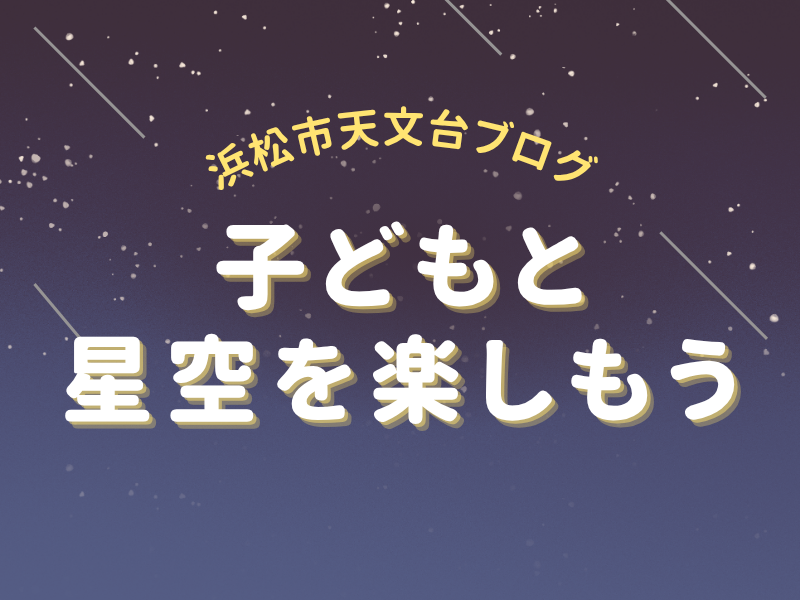子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
子育てのヒントを検索
<音楽の都>の浜松っ子たち サックス吹きへの情熱で子どもたちの楽器環境を変える『鰐田商店』店主 鰐田知典さん
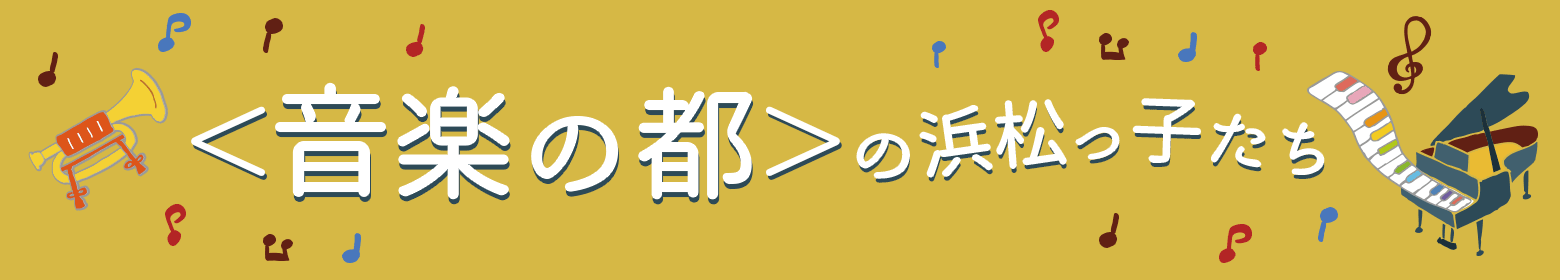
<音楽の都>を舞台に、浜松っ子たちの<音楽>にまつわるエピソードを聴くシリーズの第二弾。
浜名区於呂でサックス工房「鰐田商店」を経営し、クラウドファンディングで学校備品の管楽器修繕をした鰐田知典(わにたとものり)さん。サックス吹きに対する熱い思いをうかがった。
現在進行形で進化中の楽器・サックス
ジャズやポップス、吹奏楽などあらゆるジャンルの曲でメロディを奏でるサックス。金属部品が複雑に絡み合ってキラリと光を反射する見た目や、金管楽器と木管楽器の中間的な独特の音色にあこがれたことのある人は多いだろう。鰐田さんもその一人だ。
鰐田さんのサックスとの出合いは、母親が聞いていたラジオ。米米CLUBの曲が流れたとき「なに、このかっこいい音は!」と衝撃を受けたと言う。しかし、サックス希望で入部した中学の吹奏楽部では体が大きいという理由でチューバ担当となり、実際にサックスを手にできたのは社会人になってから。それまでしたくてもできなかったうっ憤を晴らすがごとく、どんどんのめりこんでいったそうだ。更に音楽関係の仕事がしたいとヤマハに転職。以来約18年、ずっとサックスの製造と修理に関わってきた。
「サックスは同じ時期のモデルでもメーカーがどんどん手を入れていて、触っているとだんだんわからなくなってくるんです。いろんなメーカーがいまだにいろんなことを試しています。機構が変わる楽器というのは普通ないんで。面白い楽器ですね」
「サックスの発展イコールジャズの発展とも言えますね。ジャズの歴史はたかだか100年弱なのに、これだけ名曲が生まれて、1960年代の曲をいまだにみんなが好き好きと言って聞いていて。その全盛期の10年20年でいろんなメソッド(奏法)が生まれて、それを実現するためにサックスも進化し続けているんです」
鰐田さんは作業エプロン姿のままで語ってくれた。

サックスをしたい子どもたちが困っているのは今
鰐田さんが2023年に実行したのが、クラウドファンディング(以下、クラファン)「学校備品の管楽器を修繕したい!楽器をなおそう!プロジェクト」だ。
「まともに音が出るように修理するとどう考えても10万円はかかるようなひどい状態の備品楽器を、子どもたちが持ってくるんですよ。確かに多くの吹奏楽部では担当の楽器が変わる時や引退する時に自費でメンテナンスをして楽器を返すのがルールですが、それが10万円コース、しかもこれ、君が壊したわけじゃないよね、これまでちゃんとメンテナンスせずに積もりに積もった結果が、これだよねという、そんな楽器ばかりなんです」
中学の入学式で吹奏楽部の演奏にあこがれ、入部する生徒は多いだろう。しかし入部してもまともに使える状態の楽器がなかったら… そんな部活があっていいわけがないと鰐田さんは言う。
「いろんな文化に気軽に触れて子どもたちの中で何かが起こればいいなというのが部活で、だからいろんな部活があるわけで。それができないなら極端な話、体一つでできる部活だけにすればいいじゃん、という話ですよ」
吹奏楽部の楽器はサックス以外にもたくさんあるし、部活で使う学校備品のメンテナンスの問題は、吹奏楽部だけのものでもない。鰐田さんもこの問題を考えれば考えるほど、現在の楽器業界が抱える構造的な問題や、より価格の安いものが選ばれる行政の入札制度など、壮大なところまで広がっていったと言う。しかし、考え抜いた先に一つの結論に達した。
「何年かしてこの問題が解決されたとしても、今困っている子どもたちはもう卒業しちゃっている。新たなサックス吹きが生まれようとしているのに、楽器から音が出ないからサックス吹きになれないって、そんなバカみたいな話はない。『俺というリペアマンと困っている子どもの2人の問題』だと捉えて、とにかくお金を集めて楽器を直そう」と。
何か大きな問題に直面したとき、「自分一人ではどうしようもできない」と動けなくなってしまう人が大半だろう。そんな時に「一番困っている人は誰?」「問題を最小単位まで分解すると自分にできることはあるのでは?」と考え、小さなことでも実行に移す。鰐田さんにお話を伺っていると、これが問題解決できるかどうかの分岐点なのだと気づかされる。
クラファンでは92人から目標金額を上回る126万円以上が集まり、浜松市立中学校12校分50本のサックスの修理を引き受けた。あと2本ですべての修理が完了する。

サックス吹きに愛を持って接する
寄付額をクリアしたクラファンだが、結果は「部品代で60万、修理代をまともに見積もったらゴリゴリの赤字」だったそうだ。今後「楽器をなおそう!プロジェクト」をどのように進めていくのかは思案中だ。しかしこの赤字は、金額ありきではなく「依頼のあった学校のサックスは全て直す」「たとえ金額が達成しなくても実行する」、鰐田さんの熱い思いの結果でもある。
うれしいこともあったそうだ。1つ目は、修理に行った学校の子どもたちが楽器の調整やメンテナンスの大切さを、身をもって理解してくれたこと。修理後はマメに楽器を見せに来てくれるようになったそうだ。少々の調整や修理であればその場で対応できるし、費用も少額で済む。子ども達にとっても楽器を預けなくてよいので、練習に穴をあけることがない。
2つ目は、クラファンによってサックスの修理費用が発生しなかった分、年度末に部費が余り、他の楽器の修理をすることができたと顧問の先生が言ってくれたこと。「それよ、それそれ」と鰐田さんはニヤリと笑う。
「毎日朝から晩までいろんな楽器を見て直して、修理の技術は開業してからも格段に上がりましたけど、演奏はめちゃくちゃ下手になりました。正直、サックスが好きかどうかもよくわからなくなっていますが、サックスをやっている人たちには愛を持って接しないと、と思っています。自分が唯一飯を食える技術は、サックス吹きや吹きたいと思う人たちに使いたい。『俺はこれで飯を食えるからやってまーす』という自分本位の考え方じゃ、商売続かないんで」

気軽に音楽を始められるまちに
青森県出身の鰐田さんが浜松で開業した理由は、「楽器のまちで勝負してダメだったら、どこでやってもダメだと思った」から。楽器を持つとプロ並みの腕前の人がいたり、まちの規模に対してスタジオがたくさんあったり、街なかで何かしらの演奏をしていたりと、こんな面白いまちはないと鰐田さんは言う。
そんな浜松が真の「楽器のまち・音楽のまち」になるために、鰐田さんが考えるもう一つの条件がある。
「音楽イベントや楽団など、演奏できる場がいっぱいあるのは素晴らしいことですけど、音楽をやりたいと思う人たちがもっと気軽に音楽できる環境が整っているのが、楽器と音楽のまちなんじゃないかなあ」
文/藤田麻希子
取材日/2024年4月24日