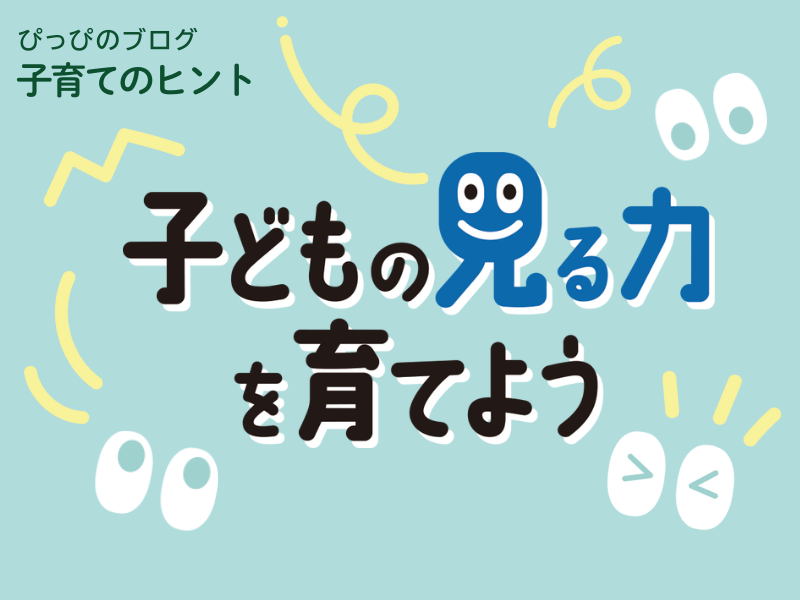子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
子育てのヒントを検索
自主防災隊&災害ボランティアがコラボした防災訓練
阪神・淡路大震災が発災してから、今年の1月17日で22年が経ちます。1995年、被災地には延べ137万人以上のボランティアが全国から集まり、「ボランティア元年」とも言われました。以来、災害が起きると、全国からボランティアが被災地に詰めかける動きが見られました。彼らボランティアを受け入れ、作業の指示やサポート、ニーズの収集などのために働くのが、災害ボランティア・コーディネーターです。浜松にも災害ボランティア連絡会があり、ぴっぴも参画しています。
昨年12月、浜松市内のある自治会の防災訓練に、「浜松市中区ボランティア連絡会」が参加し、合同で訓練を行いました。
訓練の内容は放水訓練やバケツリレー、担架や三角巾の使い方など、よく行われているものです。ですが、今回はそれに加え、子どもの参加者(今回は小・中学生)に架空の「災害ボランティア」体験をしてもらう仕掛けをしました。

当日、通常の受付隣に「ぷちボラセン(ボランティアセンター)」受付を設置。それぞれの訓練メニューの場所に行き、指導者の補助をしたり、訓練のモデルとなったりするなど、率先して動いてもらうように指示所を渡して「派遣」をしました。
「ボランティア」の名札をつけることで、意識が変わる効果があったようです。本部テントの設置や仮設トイレの組み立て、炊き出しの盛り付けなどを、大人の指示を受けながら一生懸命に行う小・中学生たちの姿がありました。

毎年似通った訓練内容だと繰り返し感が強く、遠巻きに眺めているだけ…という参加のしかたになるのも無理のないことかもしれません。しかし、今回、災害ボランティアの視点を加えることで、「自分も支援する側になりえるということ」「自分も地域で防災訓練の担い手になりえるということ」に気づいてもらえたのではないでしょうか。
訓練後の報告書には、「今まで防災訓練がめんどくさいと思っていたけれど、とても大切なものだと分かった」「私たち若者が主力となって、積極的に参加する必要があることを痛感した」などの感想があり、予想以上に「自分が主体となる」ことの効果が見られました。また、子どもが率先して動くことで、大人の参加者もより真剣に参加できたのではないでしょうか。

もちろん、実際の災害ボランティアとして活動するには、相応の装備や心得、知識、スキルが必要です。ですが、今回の“ぷちボラセン”体験により、「防災は自分ごと」と感じてもらえたことが、何よりも大きな収穫だったと感じています。
(ずきんちゃん)