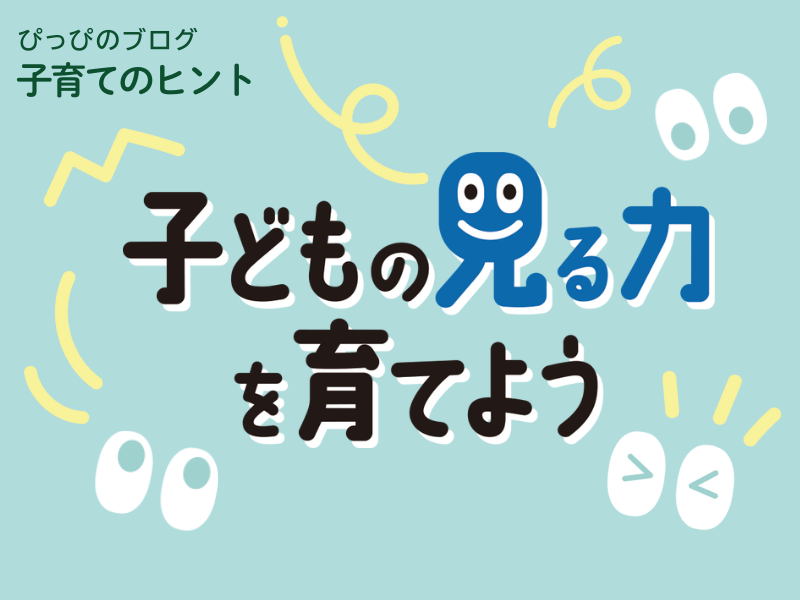子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
子育てのヒントを検索
専門家の子育て2
 GWのような長期の休み明けに幼稚園や保育園をたずねると、なかなか保護者から離れようとしない子どもたちに出会います。4月に入園して1ヶ月弱、ようやく子どもも新しい環境になれてきたのに・・・・、また初めの頃に戻ってしまったと思うお父さん、お母さんも多いのではないでしょうか。
GWのような長期の休み明けに幼稚園や保育園をたずねると、なかなか保護者から離れようとしない子どもたちに出会います。4月に入園して1ヶ月弱、ようやく子どもも新しい環境になれてきたのに・・・・、また初めの頃に戻ってしまったと思うお父さん、お母さんも多いのではないでしょうか。このように「できていたことができなくなること」を心理学では、ちょっと難しい言葉で「退行」と言います。
大人も含めて、人はピンチに出会うと、実際より低い年齢の子どものように振る舞うことがしばしばあります。
たとえば、下の子どもが生まれたとき、急に上の子がわがままになったり、時には指しゃぶりやおねしょがひどくなったり、いわゆる「赤ちゃん返り」と呼ばれるものです。
さて話を戻して、このような場面をよく見ていると、先生によって、だいたい2つの関わり方があるようです。
1つは、「子どもに関わる」という方法です。
たとえば、「今日は、○○ちゃんの好きなお絵かきがあるよ」とか「先生と一緒に○○で遊ぼう!」、あるいは友だちをつれてきて呼んでもらうなどです。
もう1つは、「保護者と関わる」という方法です。
たとえば、「先生:この休みはどこに行ってきたんですか?」、「保護者:ディズニーランドへ」、「先生:混んでいて大変だったでしょ。でも○○ちゃんはよかったね。楽しかったでしょ?」、「子:楽しかった」、「先生:そっか楽しかったかぁ。じゃぁお部屋でその話みんなにも聞かせてもらえるかな・・・・」という具合に、子どもよりむしろ、大人に関わるという方法です。
で、どちらのやり方がうまくいくのか、というのも変ですが、こういう問題にうまく対応されている先生の多くは、しばしば後者の方法をとっています。
先生の多くはこれまでの経験からこのようにしているのでしょう。
しかし、この泣いている子どもではなく、泣いている子どもの親(保護者)と関わるというやり方、実は発達心理学的にみても一理あります。
もっと小さい子どもの話になりますが、「人見知り」という現象があります。
簡単に言ってしまうと、「子どもがお母さん以外の人を見ると、泣いてしまう」現象ですが、この時、1つだけ例外があります。
それは、「お母さんと仲良くしている人」には泣かないということです。
要するに、「自分と仲の良い人と仲の良い人は大丈夫」というわけです。
さてこのことを冒頭の場面に当てはめてみると、なぜ長い休みの後、子どもではなく、保護者と関わるとうまく行くことがしばしばあるのか、ご理解いただけるのではないでしょうか。
つまり、長い休みを経ることで、赤ちゃん返りが起きて、保育者に対しても、人見知りが起きていると考えることができます。
そのときに、ちょっと発達の知識があれば、『子どもと関わるだけがすべてじゃないな』と考え、保護者と関わるという手が考えられるということです。
もちろん、先生や子どもの個性もあるので、全てにおいてうまく行くとはかぎりません。でもこのことを保護者の側から考えてみると、長い休みや、登園しぶりが起きてしまったとき、子どもを何とかするというだけでなく、いつもより5分早く家を出て、自分が先生との会話を楽しむという方法をとってみるというのも手ではないかと思います。