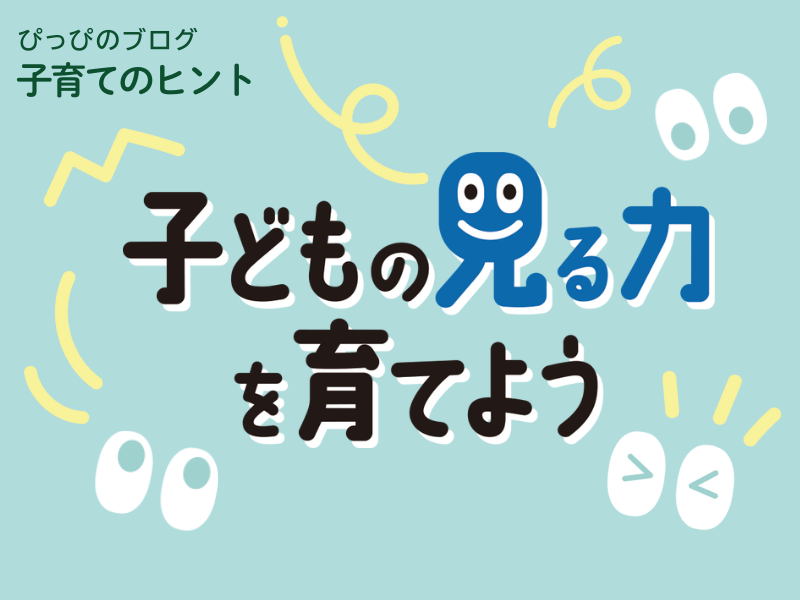子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
子育てのヒントを検索
ことばって難しい?
 こんにちは。新年度がスタートしました。
こんにちは。新年度がスタートしました。本学科でも41名の新入生を迎え、保育者としての一歩を踏み出しました。
先日2年生の授業科目の「保育内容の研究(言葉)」で、学生にことばについて3つの内容を実践してもらいました。
まずは、1人が先生役、1人が5歳の子どもの役となり課題となる折り紙を折るというものです。
先生役は用紙に示された言葉だけで相手に伝えなくてはならないという条件をつけたところ、5分経過しても作品はできず・・・。
結局、先生と一緒に作ることでやっと完成・・・。
子どもたちの前では身ぶりや手振り、わかりやすい言葉で説明をしないと伝わらないということを実感したようでした。
次はところ変われば言葉も変わる、ということである文章を3歳くらいの子どもが話す言葉で、自分の地域で使う言葉と関西方面の人が使う言葉で書いてみることをしました。
ここでも悪戦苦闘・・・静岡県内で生活をする学生にとって自分が普段使っている言葉が基準であるため、全く違う地域の言葉遣いが浮かんで来ないのです。
無理はありませんね。
核家族が増え、転勤などで地元を離れて生活する人にとって使い慣れた言葉がその土地で通用しない場合もある、なんて経験をした方もいると思います。
小さい子どもでも環境に適応するとその土地の言葉を遣っています。
関西の保育園で仕事をしていた時に、2歳前後の子どもが関西弁で必死に保育者に伝えようとしている姿に「すごい・・」と驚いたものです。
最後に、3月に実施した子育てひろばでの写真の一部分を見せ、年齢の異なる子どもたちの表情から、どのような言葉を読み取ることができるのか、学生に聞いてみました。
笑っている5歳前後の子どもを見て「おもしろい!!楽しい」と感じ、3歳の子どもを見て「何をやっているんだろう」と興味を示しているということを読み取ることができました。
しかし、1歳未満の子どもたちの真剣な表情を見て言葉を読み取ることは残念ながらできませんでした。
言葉を持たない子どもたちほど表情や仕草でわたしたち大人が気持ちを読み取り相手に言葉で伝えていくことが大切である、ということに気がつかなかったのでしょう。
と同時に0歳、1歳、2歳の子どもたちの発達が結びついていなかったという解釈もできます。
「赤ちゃんは言葉を話さない。だからどのように声をかけていいのかわからない」ととまどう学生が多いのですが「名前を呼んであげて。笑ったら『うれしいんだね』って声をかけてごらん」赤ちゃんからの反応が返って来たときの学生のうれしそうな顔が印象的でした。
小さな子どもたちとの言葉のキャッチボールって難しいですね。