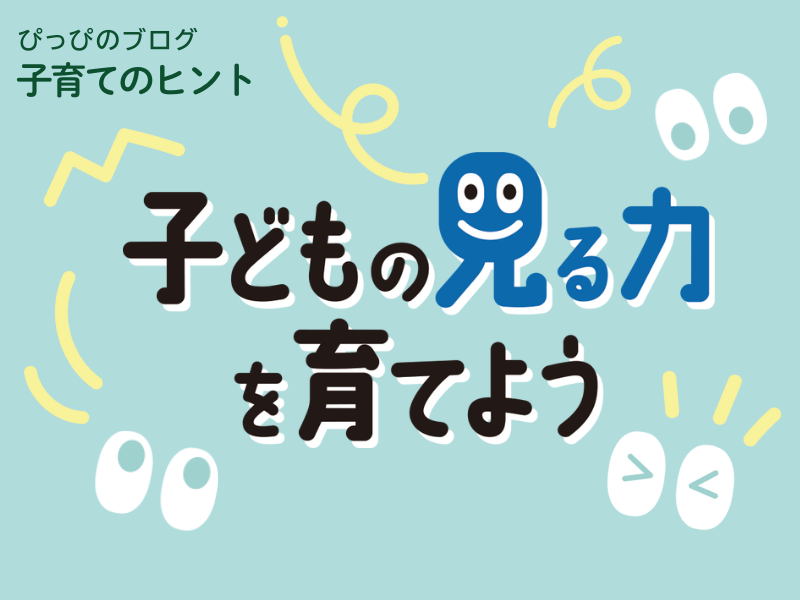子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
子育てのヒントを検索
保育園のマナー教室~助産師たちのつぶやき~
助産師の石黒です。助産師のつぶやきですが、お産とは少し離れてお話したいと思います。
つい先日、長男の保育園で行われるマナー教室に参加してきました。保育園では年長クラスを対象に毎月1回マナーの先生が来て、いろいろな事を教えてくれます。先日は12月ということもあり、年末年始の行事について教えていただきました。今まで何となく知っていたことも“なるほど、そんな深い意味があったんだ~”と、目からうろこ状態でした。そんな私にとって特に心に響いたお話をご紹介します。 除夜の鐘は108つ撞くというのはみなさんもご存知かと思いますが、107つまでは旧年(12月31日)に撞き、108つ目は新年(1月1日)に撞くのが作法って知っていますか?
除夜の鐘は108つ撞くというのはみなさんもご存知かと思いますが、107つまでは旧年(12月31日)に撞き、108つ目は新年(1月1日)に撞くのが作法って知っていますか?
その他にも先生は神社への初詣での作法もお話してくれました。
神社の鳥居をくぐる前に軽く一礼し、手水舎で両手を洗い、口もすすぐことで自分の心も清めるのだそうです。もちろん自分が使った柄杓は最後に柄までお水を流して、次に使う人のためにきれいにして戻しておきます。こうして神様へお願い事をする準備ができます。
おせちを食べる時に使う祝い箸にも意味があります。祝い箸は両端が細くなっており、どちら側でも使うことができます。しかし、自分が使っていない側は神様が一緒にお食事をするためのものなので、両方使えるからといって別の料理を取り分けるために使ったりしてはいけないそうです。他にも七草粥や鏡開き、お年玉のいただき方などなど沢山お話してくださいました。
昔は二世帯、三世帯が同居する中、日々の会話や行事から自然にこうした『神様を敬う心や人に対するいたわりの気持ち』を教えてもらっていたように感じます。しかし、核家族化が進む現代、伝統ある行事を受け継いでいくのはなかなか難しい状況ではないかと思います。でも、受け継いでいってほしい大切なものってやっぱり大事です。今回のマナー教室参加を機に、私も“なんちゃっておせち”や“七草粥もどき”などに挑戦してみたいと思います。そうした自分の姿や言葉から子どもたちが何かを感じてくれたらいいなと思います。そして、思いやりの心や人を敬う気持ちを少しずつ育んでいってくれたらと思っています。