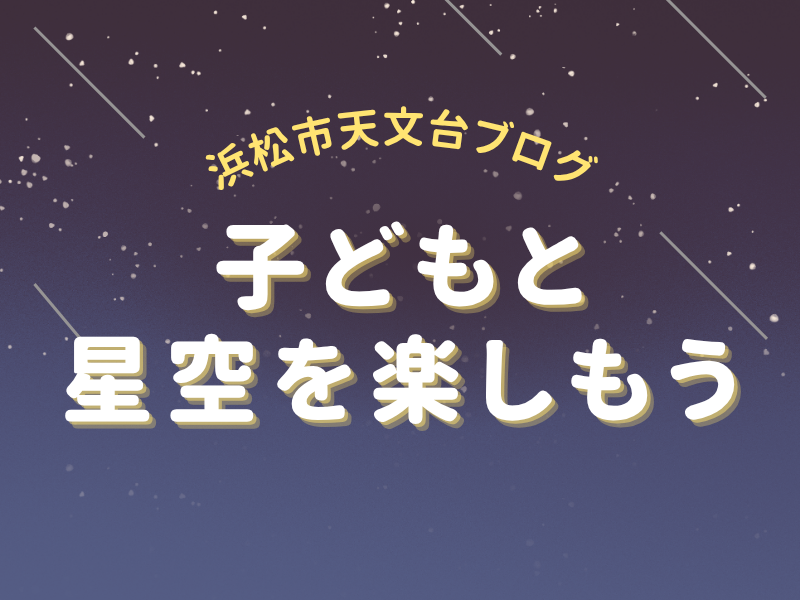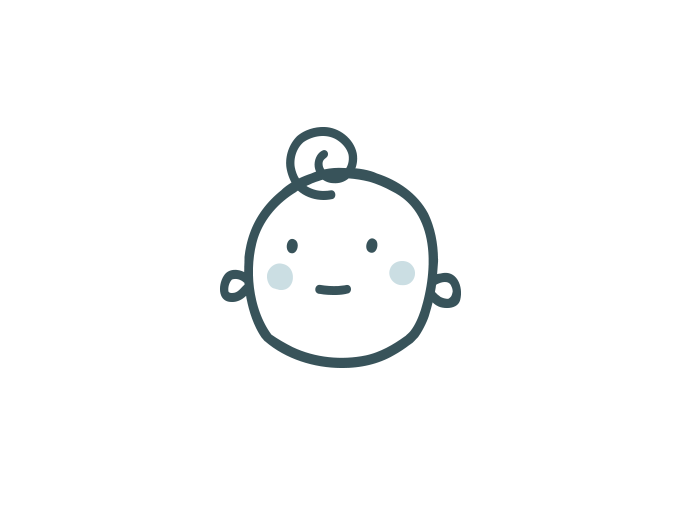子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
子育てのヒントを検索
子どもの見る力を育てよう(2)~視覚情報をしっかり取り込んで脳に伝える!(入力機能)~

当たり前のことですが、私たちの生活は見て、考えて、行動することで成り立っています。そうした力が上手に統合し、さまざまな動作を完成させているわけです。私たちの生活を支える「見る力」に関連するさまざまな機能について説明してきます。
「見て、考えて、行動する」ための脳機能
車を運転中、交差点で信号機が黄色に変わった瞬間を考えてみましょう。脳では以下の一連の作業が一瞬で行われます。
- 入力機能 信号機が黄色に変わったことを目で確認
- 情報処理機能 「これは止まらないといけない距離だ」と脳が判断
- 出力機能 足の筋肉に指令を出してブレーキを踏む
この視覚認知過程において、さまざまな視覚や運動機能が相互に協調し合い、「見る力」を発揮しています。
今回は、「入力機能」について説明していきます。これは、視覚情報を正確に素早く入力するために必要な機能です。
まず基本となるのは視力の確認です。視力検査で問題が見つかれば、近視・遠視・乱視の可能性があるため眼科を受診しましょう。
1. 両眼視機能
両眼で対象物を捉える機能です。近くを見る時は両眼が内側に寄り(輻輳・ふくそう)、遠くを見る時は外側に離れます(開散)。左右の映像のズレを脳が融像することで立体視が可能になり、奥行きや距離を認識できます。
-
映像が二重に見える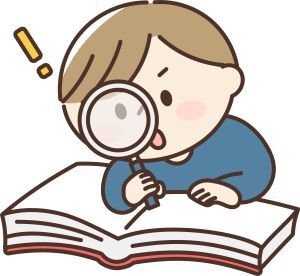
- 眼が疲れやすい
- 片目をつぶったり首を傾けて見る
- 注意集中力の持続困難、学業への影響
などがみられる時には、両眼視機能の不全があるかもしれません。
2. 調節機能
見る距離に応じて、眼の中にある水晶体(レンズ)の厚さを自動的に変えてピントを調節する機能です。なので、近いものを見続けたりすると、とても負担がかかるのです。
- 本やパソコン画面を見てすぐ目が疲れる
- 文字や画像がぼやけて見える
そんなあらわれがある時には、調節機能の何らかの不具合があるのかもしれません。
注意:スマホなど小さな画面の長時間使用は調節機能に悪影響を及ぼす可能性があります。
3. 眼球運動
対象物をはっきりと見続けるために、眼球を素早く正確に運動させる機能です。片眼に6つの筋肉が付いていて、目を動かすためにそれぞれの筋肉が協調して眼の動きを生み出しています。2つの眼球運動があります。
(1) 衝動性眼球運動 視線を物から物へと素早く移動させる機能。鬼ごっこで相手を瞬時に探す、自動販売機で目当ての商品を見つける、スポーツ競技、読書、書き取りなどに関与します。
(2) 追従性眼球運動 動いている物に視線を合わせて追う、または視線を一点に固定する機能。先生が空中に書く文字を目で追って覚える、転がるボールを捕球する、定規で線を引く、ハサミで線に沿って切るなどを支えます。
まとめ
「見る力」は、入力機能における視力、両眼視、調節、眼球運動といった複数の機能が相互に協調することで成り立っています。これらの機能に問題がある場合、日常生活や学習に様々な影響を及ぼす可能性があるため、適切な理解と対応が重要です。
次回は、考えることに重要な「情報処理過程」について説明いたします。