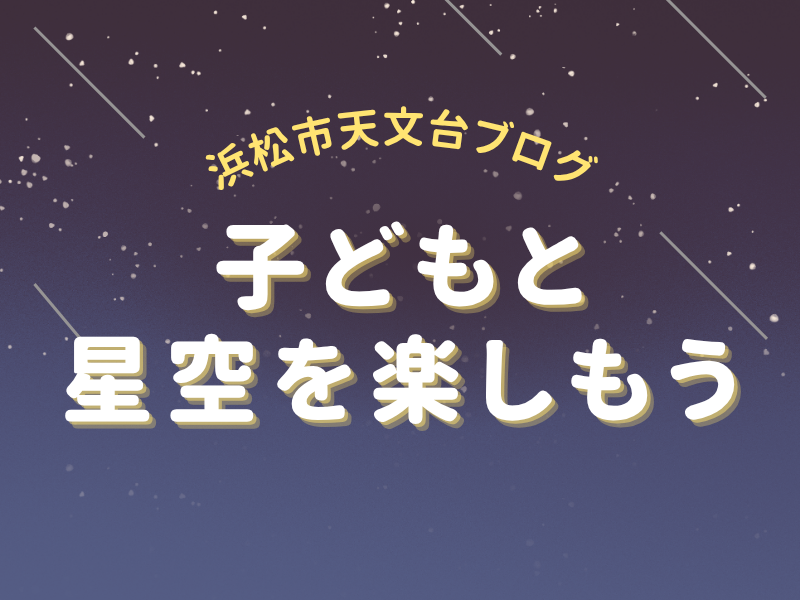子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
子育てのヒントを検索
百年後のふるさとを守る (稲村の火)
「稲村の火」は、1854年の「安政南海地震」の時の和歌山県の実話です。
地震の直後、高台から海を見て異変に気付いた浜口儀兵衛が、人の命を優先させるため、1年分の収穫である稲束に火をつけ、村民を高台に誘導し多くの命が守られたというお話です。サイレンも、テレビも、ラジオもない150年前の時代の話です。
以前のブログで、紙芝居を紹介しております。
今年度の教科書改訂で、64年ぶりに小学校5年生の国語の教科書に復活したそうです。採用が決まったのは、3月の震災よりもっと以前でしょうから偶然とはいえ驚きです。
(被災地の小学校では、今回の震災と重なる部分が多いため、子どもの心理的な負担に配慮して差し替え教材が用意されたようです。)
教科書に載っている話は、浜口儀兵衛の伝記として、防災学者の河田恵昭氏により2008年に書き下ろされたものです。
地震・津波のあと村を離れようとした、村民を引きとめ、儀兵衛が私財を投じ、村民の手による堤防づくりを進め、4年かけて完成させたことなどにもふれられています。
このとき築かれた、大防波堤「広村堤防」は、昭和21年に発生した昭和の南海地震津波から住民を守ったそうです。
浜松市内の多くの小学校では、国語の教科書の音読が毎日宿題に出ます。6月のほぼ1ヶ月間、小学校5年生の子どもが音読するのを聞いていました。とても長いので子どもも読むのも大変ですが、大人にとってもすごく学ぶことの多い文章でした。
津波対策・防災対策はもちろんですが、災害後の地域の再生、復興政策の在り方などについても大事なことを教わりました。
最後はこうまとめられています。
災害後の対応と防災という観点から見ても、儀兵衛の堤防づくりには大きな意義がふくまれている。
その一つは、物質的な援助だけでなく、防災事業と住民の生活援助を合わせて行ったことである。
また、住民どうしが、たがいに助け合いながら、自分たちが住む所を守るのだという意識をもつようにうながしたことも大きい。
ほかのものにたよるのではない、自助の意識と共助の意識である。
現代でもいえることだが、これがなくては、災害後の真の再生は望めない。
今日ならば、ここに町や県、国などの公助が加わるのは当然である。
さらに、百年後という長期計画の必要性と有効性を教えてくれたことである。
安政の大地震のような大災害は、百年単位で起きる。
百年先の子孫のためにということは、口では言えても、なかなかできることではない。
それを、儀兵衛は行い、実際に大いに役立ったのである。
地震の多いこの国に生きるわたしたちは、儀兵衛がしたことや考えたことから、多くのことを学ぶとができる。
また、学ばなければならないだろう。
光村図書 国語 五 銀河「百年後のふるさとを守る」 より一部引用
はっぴー☆