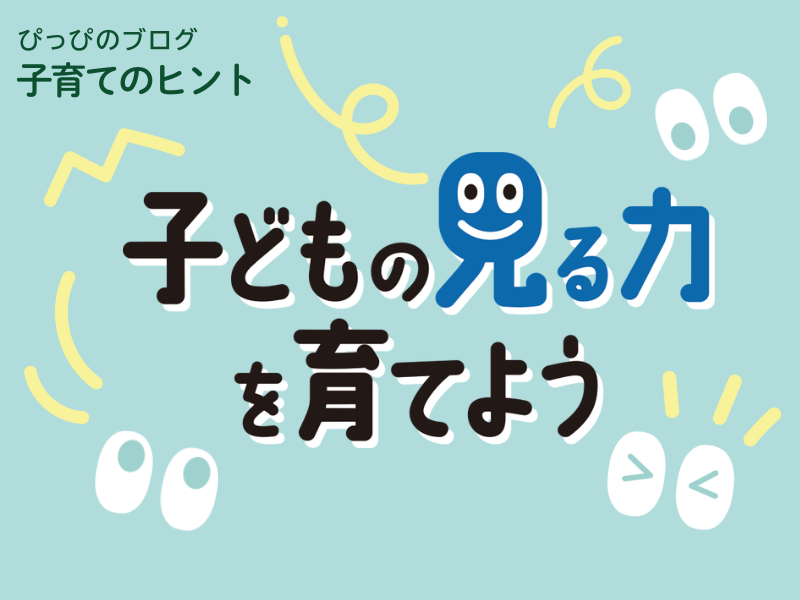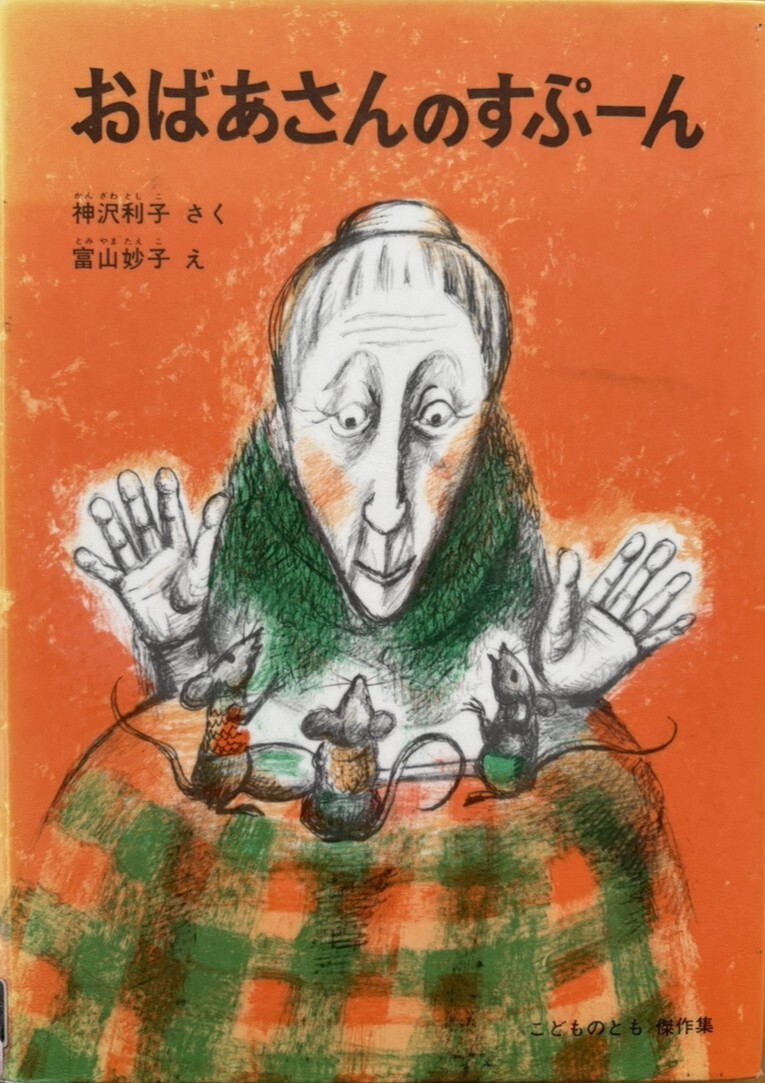子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
子育てのヒントを検索
子どもの見る力を育てよう(5)子どもの「見る力」と「動く力」をつなぐ身体感覚の育て方

公園でキャッチボールをしている時、お子さんがボールを上手にキャッチできた瞬間を思い浮かべてみてください。あるいは、お箸で小さなおかずをつまんで口まで運ぶ姿。一見何気ない動作ですが、実はこれらには「目で見た情報」と「体を動かす力」が見事に連携しているのです。
この連携がスムーズに育つためには、自分の体をどう感じ取り、空間の中でどう捉えるかという”身体感覚の土台”が大切です。今回は、この土台となる4つの力について、具体的な場面を交えながらご紹介します。
1. 身体部位の認識(ボディ・パーツ)
自分の体の地図を持つこと。
「右手を伸ばしてボールを取る」「足を高く上げて段差を超える」こうした動作ができるのは、頭の中に"自分の体の地図"があるからです。
<こんな場面で気づきます>
給食の時間: スプーンを握る力加減が分からず、強く握りすぎて疲れてしまう
着替えの時: 服の袖に腕を通すのに時間がかかる
体育の時間: 「腕を大きく回して」と言われても、どう動かせばいいか戸惑う
2. 身体空間認知(ボディ・スキーマ)
体が空間のどこにあるかを感じる力。
これは「物との距離感」「自分の体の大きさ」「どのくらい動けば届くか」を無意識のうちに判断する力です。
<こんな場面で活躍します>
廊下を歩く時: 他の子どもや壁にぶつからずに歩ける
縄跳びをする時: 縄が回ってくるタイミングで飛べる
ノートに書く時: 文字の大きさや位置をそろえて書ける
3. ラテラリティ(左右の認識)
右と左をはっきり区別する力
これは単に「右手・左手を知っている」だけではありません。体の動かし方や方向性に深く関係しています。
<こんな場面で大切です>
字を書く時: 「はらい」や「とめ」の方向を正しく認識できる
ドッジボールの時: 「右から来たボールに、その方向を向いてよける(または捕る)」判断ができる
算数の時間: 図形の向きや鏡文字に惑わされない

身体感覚が育つことで、お子さんの日常にこんな変化が現れます。
- 目と手がそろって動き、工作や書字が楽になる
- 人や物にぶつかることが減る
- 「こぼす・落とす」が少なくなる
- 体育や遊びで動きが軽やかになる
- 急な変化にも素早く対応できる
- 「自分でできた!」という自信が育つ
ご家庭で楽しくできる遊びのヒント
特別な道具がなくても、日常の中で身体感覚を育てることができます。
- 左右タッチゲーム: 「右手で頭、左手でお腹!」など、左右を意識した指示遊び
- ボール転がし: ゆっくり転がして「ここで止めてね」と距離感を練習
- 体の部位クイズ: 「肘ってどこ?」「膝の上は?」と体のパーツを確認
- 距離予測遊び: 「あのおもちゃまで何歩で着くかな?」と予測してから歩く
ポイントは、「楽しい!」と感じられること。無理なく、遊びの中で自然と育てていきましょう。
まとめ
視覚と運動の協調は、「目が良い」「体が強い」ということではありません。自分の体をどう感じ取り、空間の中でどう捉えるか。この"身体感覚の土台"によって、お子さんの動作は滑らかになり、学習や遊びの経験が豊かに広がっていきます。
日々の遊びの中で、お子さんと一緒に楽しみながら、身体感覚を育ててみてください。小さな積み重ねが、大きな成長につながります。