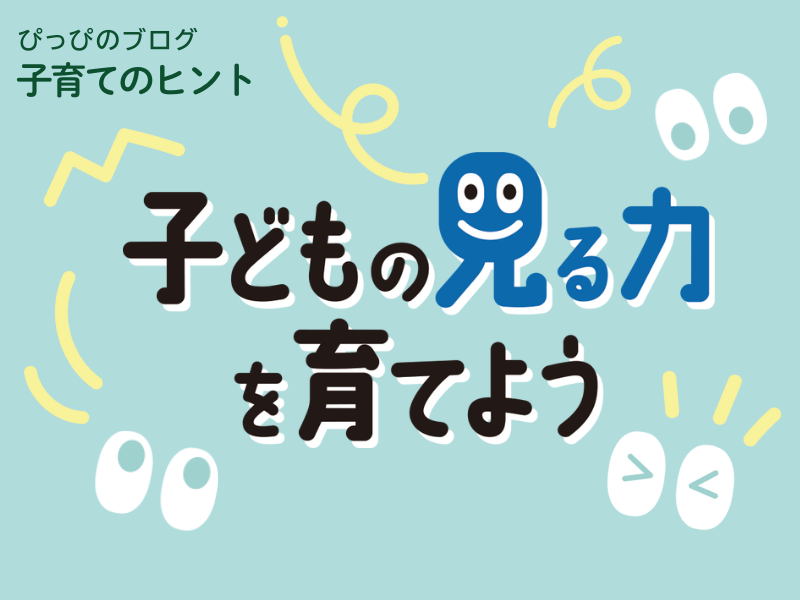子連れでおでかけ
子育てのヒント
特集記事
子育てのヒントを検索
産後パパ育休・育休を考えてみませんか 助産師たちのつぶやき

木の芽や花のつぼみのふくらみに生命の息吹を感じる嬉しい季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、今回は『産後パパ育休(出生時育児休業)』と『育休(育児休業)』について考えてみたいと思います。最近では、当院でご出産される方の半数近くの旦那さんが育休をとっている印象を受けます。ここ数年で妊婦健診に旦那さんと一緒に来られる方も増え、男性の妊娠・育児への興味や意識が急激に変化してきているのを感じます。
2023年度の政府調査では、男性の育休取得率が初めて30%を超えたと発表されました。これは、2018年度と比較すると5年間で約4倍となっており、近年急激に取得率が上昇していることがわかります。ちなみに政府としては、2025年度に50%、2030年度に85%の取得率を目標としているそうです。
さて、皆さんは男性が取得できる育休が2種類あることをご存じでしょうか?いわゆる以前からある『育休』とは別に『産後パパ育休』というものが2022年に制定されました。これは、男性が育児休業を取得しにくい社会的背景を踏まえて新たに誕生した制度です。

育休は子どもが1歳になるまでの間で取得可能ですが、原則その間は仕事ができないのに対し、産後パパ育休は子どもの出生後8週間以内に最大28日間(2分割可能)取得可能で休業中でも一定の条件下であれば仕事をすることが認められています。そして、どちらの制度も育児休業給付金(原則休業開始時の賃金の67%・180日経過後は50%)が受けられます。産後パパ育休と育休は別の制度になるため、両方の制度を利用することが可能です。例えば、出生後8週間までの間に引き継ぎや重要な会議などに出席しながら産後パパ育休をとり、その後に育休を長期間とることができます(もちろん、産後パパ育休をとらずにそのまま育休をとることも出来ます)。制度の詳細については、ご自身でもよく調べてみてください。
直接おっぱいをあげる以外はパパだって何でもできます!かわいいわが子のお世話を大好きな奥さんと一緒に経験できるなんて今しかありません。ぜひご夫婦でよく話し合って、自分たちに合った家族のカタチを探してみてくださいね。
ちなみに、時々「会社から前例がないため育休は取れないと言われた」という方がいます。育休の取得は『育児・介護休業法』という法律に明記されている労働者の権利であるため、会社の対応に納得できない場合は社内の相談窓口や労働組合、労働局に相談してみてください。
文/浜松医療センター周産期センター 助産師 葛綿優子