あいさつをしません。どのようにしたらあいさつをするようになりますか。
どうすればあいさつができる子になる?
まずは大人のサポートが必要
あいさつは、コミュニケーションの基本となるため、日頃から習慣づけさせたいものですね。
あいさつには、さまざまなものがあります。
例えば、「おはようございます」「こんにちは」「こんばんは」「いただきます」「行ってきます」「ただいま」「おかえりなさい」「ありがとうございます」「ごめんなさい」「おやすみなさい」など、いろいろなものがあります。
大人は、あいさつをする相手や場面に応じて、何気なくあいさつの言葉を使い分けていますが、子どもにとっては、少し難しいものです。
日頃の生活の中で、子どもが生活の場面に応じたあいさつをするには、周りの大人のサポートが必要です。
大人と一緒にあいさつをする
子どもがあいさつをしない理由は、いくつか考えられます。
- あいさつを知らない
- どのようなあいさつをすればいいか分からない
- あいさつをするタイミングが分からない
- 恥ずかしい、または、親の前で人にあいさつをするのが恥ずかしい
- あいさつをする気分ではない
子どもにもあいさつをしたくない時(例えば、何かに夢中になっている時・機嫌や体調が優れない時等)があります。子どもにあいさつを無理強いすると、あいさつは叱られるもの・嫌な思いをするもの、という悪い印象になり、プレッシャーを感じたり苦手になったりする場合があります。
あいさつをするのが恥ずかしいという場合には、まずは家の中だけで身近な人とあいさつをしてみたり、「一緒にあいさつをしてみよう」と安心する声掛けをしたりし、子どもがあいさつをするタイミングを待ちましょう。
また、子どものあいさつに大人が応えることも大切です。
例:子「いってきます」→大人「いってらっしゃい」
子「おやすみなさい」→大人「おやすみなさい」等
そして、子どもがあいさつをした際には、「○○ちゃんがあいさつしてくれたから、元気が出たよ」、「○○ちゃんがあいさつをしたら、お友達が嬉しそうにしていたね」などと、気持ちよくあいさつを交わせて良かったねということが感じられる声掛けもしてみましょう。
上記を踏まえて、大人は、次のようなサポートをしてみましょう。
大人が家や外であいさつをする姿を見せる!
子どもは、身近にいる大人の姿を見ながら成長します。大人があいさつをする姿を見たり真似をしたりする中で、子どもはあいさつの言葉やタイミングを覚え、少しずつ身に付けていきます。
子どもがあいさつをしなくても見守る!
子どもにあいさつをしてほしいという願いから、叱ったり強制的に言わせたりすることは避けましょう。
あいさつをする心地良さを味わえるようにする!
あいさつは、相手に自分の気持ちを伝えること・相手に元気を分けること・相手と仲良くなるきっかけになることなど、あいさつの大切さを子どもに伝えていきましょう。
あいさつは、教えたからといって、すぐに身に付くものではありません。周りにいる人と接する中で、あいさつをしたりあいさつをしてもらったりする心地良さが味わえるといいですね。
子どもが外に出て、あいさつだけではなく、話をしなくなったり、反対にパニックになってしまったりする場合は、園の先生やかかりつけ医、こども家庭センター等に相談をしましょう。


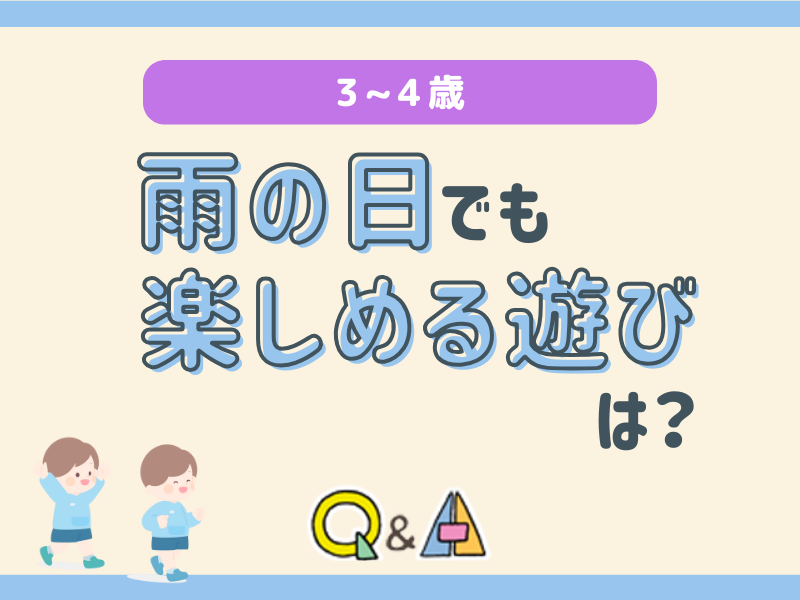
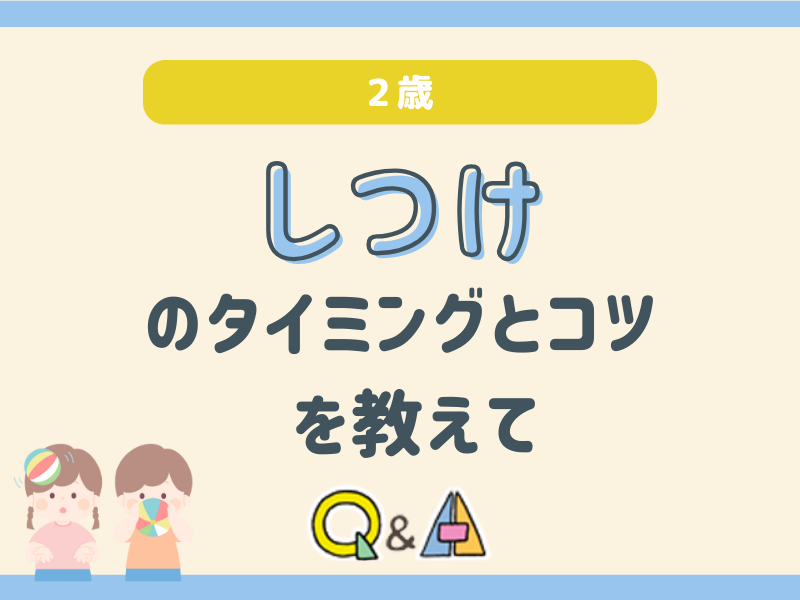



防災や防犯の視点からも、日頃からの地域の人とのつながり作りは大切で、あいさつはそのきっかけとして、とても重要です。近所の人にあいさつしたり、子育て支援ひろばなどに行って同年代の家族とあいさつをしたりして、いろいろな場面でかわすあいさつを、子どもに経験させたいものです。